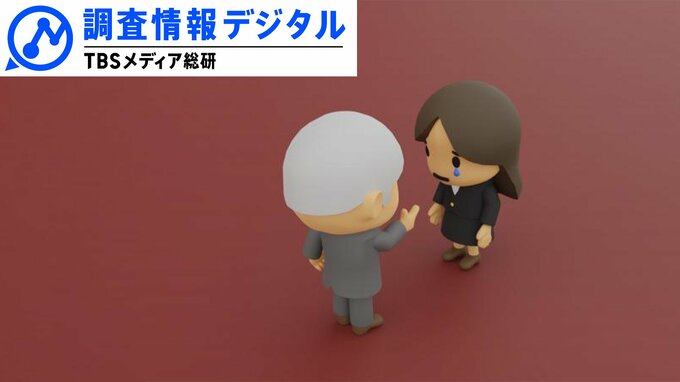近年、問題視されることの多い「カスタマーハラスメント」。難しいと言われるその線引きはどう考えればよいのか。さらにその複合的要因と有効な処方箋を、予防医学者で保健学博士の島田恭子氏が探る。
カスタマーハラスメントとは
――「自分の感情をそのまま支離滅裂な大声で怒鳴りつける。バカ、ボケなど人格を否定するような発言。物価高騰のため、と説明したら『なにを偉そうに、何が物価高騰だ』と大声で怒鳴られた。自分の都合でイライラしているお客様があまりにも多いです」
――「『お客は神様なのに、神様に意見するな』と言われた」
――「購入した商品の使い方がわからない、店員の説明が悪いからだから、家まできて説明しろといわれ、怖がった従業員がはい、と言ってしまったため、付き添いで行きました。そこで使い方を説明したが納得されず、3時間ほど説教され拘束されました」
――「罵声、椅子を蹴られるなど。不当なクレームの繰り返し。それまでに多くの対応者の労力を奪った。組織の方針でひたすら謝罪をする傾向にあり、被害を受けた者は、会社から守ってもらえていないと感じることで二重に傷ついている気がする」
読んでいるだけで気分の悪くなるようなコメントが目に飛び込んできます。筆者らが分析を手掛けた、カスタマーハラスメント実態調査(労働組合UAゼンセン、2024年)から引用したものです。
カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)とは、人と接する仕事、いわゆる対人関係を伴う業種(小売りなどのサービス業、市役所や学校教育機関、医療介護福祉業など)において、顧客に相当する立場の者から、対応者である従業員に対して行われる、精神的・身体的な攻撃行為などの、不快で非常識な言動、常識やサービス範囲を逸脱した不当な要求を指します。
近年この問題は、労働力不足やコロナ禍などの社会情勢も相まって、社会的に大きな関心を集めており、企業や自治体などで様々な対策が始まっています。2022年2月に厚生労働省が発表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、その具体的な対策の助けとなるように、カスハラの定義、具体例、従業員がカスハラを受けた際の対応方法や組織がとるべき防止策について言及されています。
このマニュアルは、カスハラが、「就業者にとって著しく就業環境を害するものである」ことを示しています。たとえば従業員に対する土下座の強要、胸ぐらをつかむ、長時間にわたりしつこく繰り返しクレームを言い続ける、といった悪質な行為は、就業環境を著しく害することが容易に想像されますし、従業員の心身の健康を損ねうることも推察できます。しかし、「悪質な行為」といったときの具体的な基準はどこにあるのでしょうか。