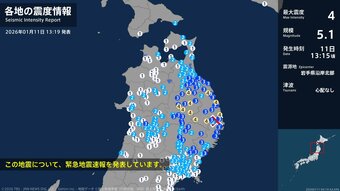取材を終えて
スイスで安楽死しようとしたくらんけさんが、日本に戻ってから3年。私は2024年2月、再び九州地方に住む彼女のもとを訪ねた。
「あの時、死んでおけばよかったという思いは日増しに強くなっていて、ただ後悔するばかりの日々です。死ななかったからといって病気が治るわけではないし、あらためてそれを突きつけられた気がしました。今も安楽死したい思いは、全く変わっていません」
そう話すくらんけさんは、帰国後に自身のこれまでの人生と体験を記した1冊の本(「私の夢はスイスで安楽死」(彩図社))を出版した。そこには、安楽死を選択する「娘の意思を理解しなければならない」と思いながらも、「それでも生きてほしい」と切実に願う両親の苦悩の言葉が紹介されている。
「可能な限り『娘が望む人生の送り方』を、親としてこれまで以上に支え受け入れる努力をしたいと思っています」(父)
「私の願望が娘の苦悩を上回ってしまっている自覚はある」「できる限りずっと私が支え、一緒に過ごしたい思いは変わらない」(母)

私は初めてくらんけさん(当時28)と会った際、このケースで安楽死が認められるのは適用範囲が広すぎるのではないかと、内心思っていた。
しかし、20年以上にわたる闘病生活が彼女の人生に与えたダメージの重さは、私の想像をはるかに超えていたことを、5年にわたる取材を通して痛感している。
彼女は今も「死にたい自分」と「生きてほしい家族」の狭間で生きている。そんな彼女に、私は「あなたにとって、家族とは何ですか」と尋ねた。
「家族は私の生命線の最後の砦です」