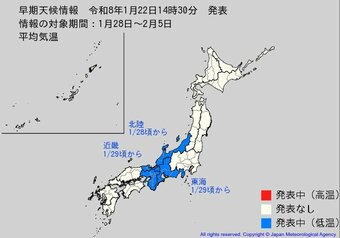「小切手1億円」の「耳」
若狭は妻が亡くなってから1年間、特捜部の「直告班」で、なんとか仕事と子育てを両立していたが、2000年4月についに現場を離れることになった。やはり子育てをするには、第一線から離れてしばらくは、ゆっくりした職場環境が必要だった。そして「最高裁判所司法研修所」に検察教官、司法試験考査委員として着任した。
現場を離れたのは初めてだった。
「その年の春、桜ってきれいだなとあらためて感じられて、正直、うれしかった。よく司法修習生たちと懇親会をやったり、差し迫った責任もなく、のびのび過ごすことができた。特捜部とは180度、まったく違う場所に移って、心身がリフレッシュできた」
しかし、特捜部の現場を離れた若狭には、こんな思いがあった。
「東京地検特捜部という政界に切り込む、独自捜査ができる部署にいたにもかかわらず、妻の看病で、十分に働くことができず「不完全燃焼」に終わったという悔いが、いつも心のどこかにあった」
そして時は流れ、妻の死から4年が過ぎていた。やがて子供も大きくなり、育児の負担も徐々に減り、環境の変化もあったことから、2003年4月、若狭は再び、念願の東京地検特捜部へ復帰することになった。3度目の特捜部だった。
若狭はもう一度、特捜部でやれるチャンスを与えられた喜びで一杯だった。胸が高鳴っていた。手を上げて現場の一兵卒のキャップを希望した。同期(35期)は、すでに副部長になった検事もいたが、そんなことはどうでもよかった。
「とにかく、もう一度特捜部で捜査に関わることができることだけでありがたいと感じた。特捜部時代に燃焼できなかった空白、不完全燃焼を晴らしたいという気持ち、もう一度とにかく現場でやりたいと志願した」
希望通り、特捜部の第一線でキャップを務めることになり、仕事に邁進した。するとキャップになってしばらく経ったある日、のちに政治家の摘発につながる一つの情報が舞い込んできた。「『りそな銀行衆議院支店』の口座に『3000万円』が入っている」と記された一枚のハガキの投書だった。
若狭は、ただちにその銀行口座を調べて、名義人から事情を聞いたところ、どうやら「日本歯科医師連盟」に疑惑があることが見えてきたのだ。そのため「日本歯科医師連盟」の家宅捜索に踏み切った。そして捜索で押収した大量の証拠物の「ブツ読み」を続けていると・・・
ある日、段ボールの中から若狭みずからが、「小切手1億円」の紙片、いわゆる「耳」を発見したのである。若狭は「これは大事件に発展する」と直感的に感じたという。しかも、調べを進めると、その1億円は、自民党旧橋本派に流れた疑いが濃厚だった。
妻の死から再出発を期する若狭を奮い立たせた。
「一気に脳内にアドレナリンが放出された。そんな気持ちになるくらい、興奮状態だった」(若狭)
さらに「政治資金収支報告書」にも記載がないことがわかり、すべて「闇の金」である可能性が高いことが判明する。若狭は慌てて、当時の特捜部長・井内顕策(30期)に報告した。井内は「ゼネコン汚職」をはじめ、「野村証券・第一勧銀の総会屋事件」「大蔵省接待汚職」「中尾栄一事件」「西武鉄道事件」など、政官財が絡む多くの大型経済事件に携わり、捜査を熟知した指揮官だった。永田町からも恐れられる存在だった。
報告を聞いた井内は、血相を変えてこう言った。
「おい若狭、これ大変なことになったよ。もう上げ下げできなくなっちゃうよ」
つまり、「証拠」が目の前にある以上、やるしかないということだ。この「小切手1億円」の「耳」が端緒となり、特捜部は、「日本歯科医師連盟」から自民党橋本派「平成研究会」へ「1億円」が流れていたことを突き止めた。
まず、献金をした側の「日本歯科医師連盟」の会長を逮捕、起訴した。これを突破口に、2004年8月29日、ついに橋本派の事務所「平成研究会」の家宅捜索に踏み込んだ。さらに自民党最大派閥・橋本派の会長代理でキーマンだった、村岡兼造元官房長官を在宅起訴したのである。(いずれも後に有罪確定)

事件の公判では、橋本派に流れた「1億円」の処理をめぐって、橋本龍太郎元首相や野中広務元幹事長、青木幹雄自民党参議院議員会長ら、超大物が証人として出廷した。
橋本元首相は特捜部に事情聴取を受けたが、嫌疑不十分で不起訴、野中広務元官房長官についても不起訴(起訴猶予)となったが、特捜部が政権中枢の本丸に切り込んだことは、自民党に大きな打撃を与えた。橋本元首相は責任をとって橋本派会長を辞任、派閥からも離脱、2005年の衆院解散で政界を引退したのである。
若狭はこの間、寸暇を惜しんで捜査に没頭した。
「特捜部に復帰してからの感覚は、1日の仕事するたびごとに、もう365日分のうちの、1日が終わってしまった、、、そしてまたあっという間に、365日分の10日が終わってしまった、、、という感覚で生きていた。その日その日に、全力投球できる充実感でいっぱいだった。初めてそんな感覚になった」(若狭)
この日歯連事件は、国会議員が摘発されるたびにクローズアップされる「政治とカネ」の問題をあらためて、浮き彫りにした。
1988年のリクルート事件の反省などを踏まえ、1995年の「小選挙区制導入」と同時に始まった「政党助成金(政党交付金)制度」は、国民1人当たり250円、年間約320億円の税金を政党に配るというものだ。
その後、1999年に「企業・団体」から「政治家個人」への政治献金は禁止されたが、「政治団体」同士の献金は規制がなかった。それが、この事件をきっかけに「政治団体」間の献金が上限、5000万円に規制されることになったのである。
若狭は、再起をかけてカムバックした特捜部で、事件を掘り起こした。一連の捜査では、診療報酬引き上げをめぐる贈収賄事件や、日歯連に関係の深い国会議員による資金横領事件なども発覚。最終的に日歯連幹部6人、自民党国会議員2人、自民党派閥会計責任者、地方議員5人など計16人が起訴され、全員の有罪が確定した。
また自民党では田中、竹下、小渕、橋本と多くの首相を出してきた「経世会支配」が弱体化する転換点となり、事件翌年、2005年に行われた衆議院議員総選挙、いわゆる「郵政選挙」で、平成研は党内第一派閥の座を森派(のちに安倍派)「清和会」に明け渡すことになった。
若狭は、燃焼できなかった「空白の時間」を埋めるかのように、駆け抜けたのであった。