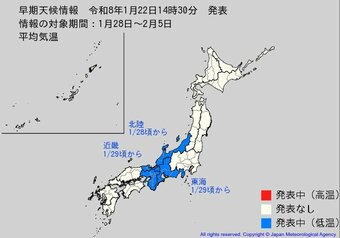妻にがんが見つかる
若狭の妻に「大腸がん」が見つかったのは1996年10月だった。東京地検特捜部はこの頃、「SEC」証券取引等監視委員会から、ある報告を受けていた。「野村証券」から「総会屋」小池隆一への利益供与の端緒だった。特捜部は「SEC」と連絡を取り合いながら、のちに「総会屋事件」「大蔵省接待汚職事件」につながる内偵捜査を始めた。
妻は、定期の健康診断で、ある項目がひっかかり、専門医による精密検査を受けた。数日後に検査結果が出たが、医師から呼び出しを受けたのは、なぜか若狭だけだった。若狭は、状況から「半ば覚悟していた」というが、やはり医師の口から出た言葉は「大腸がんです」という告知だった。まだ長男が小学6年、長女が小学4年のときだった。そこから、妻の療養生活が始まった。
若狭は当初、医師から「手術で切除すれば大丈夫」と説明を受けていたこともあり、死に至るような重篤な状態だとは全く考えていなかった。手術さえすれば、完治して元通りになるという感覚だったのだ。だが、治療を続けていくうちに、最初に抱いていた楽観的な状態ではないことに、徐々に気づかされる。
一度は手術に「成功した」と言われたが、全身のMRI検査をみると、やはり結果が思わしくなかったのだ。しかも、その後、がんの転移がわかり、次第に若狭の心配は募り、不安は大きくなっていった。
子供たちは、どう受け止めていたのか。
「重い病気であることは、子供たちも理解していたが、がんと言っても、それがどういう病気なのかは、おそらく分かっていなかったかも知れない。とくに娘は、まだ小学4年、あまりピンときていなかったのではないかと思う」(若狭)
一方、特捜部の捜査だが、大蔵キャリア、日銀キャリア、4大証券、第一勧銀の首脳らの逮捕者は
51人に上った。起訴されたのは39人という空前絶後の規模だった。
大蔵省は1998年4月、大物の「大蔵キャリア官僚」ら、MOF担などから過剰接待を受けていた職員112人の大量処分を発表。これにより「大蔵省接待汚職」の捜査は、事実上終結した。世間は検察と大蔵省が「手打ち」をしたとのではと受け止めた。
若狭の上司の熊﨑は、特捜部長から24期のトップを切って1998年6月、富山地検検事正へ栄転した。だが、筆者ら司法記者との送別会では「まだやり残したこともあった」と話していた。大手生命保険会社から大蔵キャリア官僚への接待や、大蔵省の叙勲の選定に便宜を図った大物大蔵キャリア官僚に対する収賄容疑が浮上し、現場は内偵捜査を続けていたが、1年以上にわたった捜査は「時間切れ」だった。
取材していた筆者にとっても、証拠関係が揃っているとされた大蔵キャリアの立件が見送られたことは、腑に落ちない着地でもあった。だが、法務・検察には「これ以上やったらきりがない」という判断もあった。これについては、改めて記したい。
若狭の妻は、2年あまりにわたる闘病の末、1999年2月11日、息を引き取った。享年42歳という若すぎる死だった。
妻の葬儀は、東京・荒川区の「町屋斎場」で営まれた。驚いたことに、そこには当時の検察庁のトップである北島敬介検事総長(13期)など、多くの検察首脳が参列していた。

目立たない41歳のヒラの特捜検事、しかも本人でなく、妻の葬儀に、検事総長ら検察首脳が弔問に訪れるのは異例中の異例だった。
それは、すでに富山地検に異動していた熊﨑が、あらかじめ検察首脳たちに若狭の事情を伝え、声を掛けていたからだった。妻を見舞いながら、黙々と仕事をこなしていた部下、若狭への最大の敬意だった。

若狭は、熊﨑の思いやり、心遣いが身に染みた。特捜検事を続けながら、勤務時間を制限して毎日、妻に会うことができた。亡くなったときには、まさか葬儀に検事総長が来るとは想像もしていなかった。
妻の死後、若狭は一人で子育てをしなければならなくなった。さすがにこのまま政財界の汚職事件の捜査に携わる余裕はなかった。そこで、特捜部のなかでも告訴・告発や交渉事を受け付ける「直告係」に配置換えを申し出た。そして家庭では、悲しみのどん底のなかで、シングルファーザーとしての生活がはじまった。
子供たちはそれぞれ、長男が中学2年、長女が小学校6年になっていたが、まだまだ母親を必要とする年齢である。最も大変だったのは、子供たちの心のケアだったという。母親を亡くしたショックと悲しみで、情緒が不安定となっていたからだ。
若狭は、当時を回顧する。
「登校前に、学校に行きたくないというトラブルは日常茶飯事で、中学2年の長男は『俺は死ぬ』と叫ぶことさえあった。中学2年生の14歳と言えば、最も多感な時期で、難しい年頃だった。ただでさえ反抗期などがある年齢。それまでは真面目に通学して成績も悪くなかったが、母親が病死したことは、頭で理解していても、心がついていかなったのだろう。遅刻したり、休む回数も増えた。学校によく呼び出され、先生との話し合いを持つ時間が増えた」
特捜検事の家庭はよく「母子家庭」と言われる。長年、妻が担ってきた子供の世話は、若狭にとって初めて経験することばかりだ。こうして子供たちと向き合いながら、孤軍奮闘した。