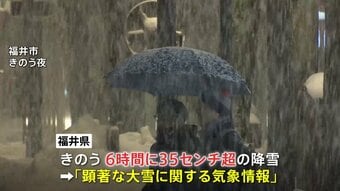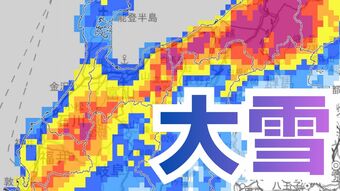「金融緩和の度合いを調整」という新たなロジック
金融緩和の度合いとは、実質金利のことを指しています。確かに日銀の政策金利は、マイナス0.1%から、3月に0~0.1%、そして今回0.25%へと、合計0.35%引き上げられましたが、予想物価上昇率を差し引いた実質金利で見れば、むしろ金融緩和は強化されていると解釈できます。
デフレ時代の予想物価上昇率はゼロ%、今の予想物価上昇率を仮に日銀がめざす2%とすれば、デフレ時代の実質金利は、マイナス0.1%ですが、今は、0.25-2=マイナス1.75%、となります。
利上げにもかかわらず、実質的にはむしろ緩和が進んでいるので、少しずつでも調整する必要があるという論理です。
それ故、「少し早めに調整した方が、後が楽になる」という植田総裁の発言につながっているのです。
ロジック変更で、むしろ不透明感も
こうなると、どこまで実質金利で見た調整を行うのかと、市場は不安になります。
予想物価上昇率が本当に2%まで上がったのだとしたら、名目金利も2%まで上げなければ、実質金利は同じになりません。
「この辺で」と言われてしまうと、「物価目標の達成確度で」というこれまでの説明よりも遥かに曖昧なので、市場は疑心暗鬼になりかねません。
円安けん制の意味もあって、植田総裁が「引き続き金融緩和の度合いを調整していく」と発言したこと、さらに、過去30年で最も政策金利の高かった0.5%についても「特に壁とは意識していない」と述べたことも、そうした不安に拍車をかけたようです。