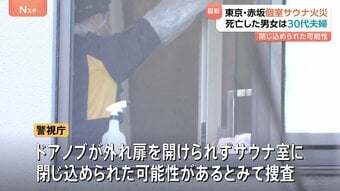沖縄県にホントに2千円札があるの?
――2千円札が今でも県内で使われているというのは本当ですか?
琉球銀行担当者:
「はい、他の紙幣と比較すると目にする機会は少ないですが、県内では日常的に利用されています」
――日常的に使われているんですね
「2千円札を出せるよう、沖縄県内のATMの機器やシステムを更改しているため、県内各銀行のATMでは、今でも2千円札で現金を引き出すことができます」
――ATMで2千円札が使えるんですか?
「はい、沖縄県内ではコンビニATMでも同様に2千円札で現金を引き出すことが出来ますよ」
沖縄県民にとって、2千円札はコンビニのATMでも手軽に手に入るほど身近な存在のようです。しかしなぜ、これほどまでに沖縄県では2千円札が浸透しているのでしょうか?
沖縄県に2千円札が浸透したワケ
ネット上では、沖縄で2千円札がよく流通している理由として「デザインに対する親近感」のほかに「米軍統治下時代に偽札警戒で使いにくい100ドル札より利便性のあった20ドル札になじみがあった」などが挙げられていますがこれらはどこまで本当なのでしょうか?
琉球銀行担当者:
「沖縄県内では、米軍統治下時代にB円(この時代に使われていた紙幣)や米ドルで『2』の付く紙幣を利用していた歴史が有る事は事実です」
――じゃあ「20ドル札になじみがあったから2千円札も沖縄県に浸透した」というのは本当だったんですか?
「いえ、現実的な所では県全体のATMなどの機器およびシステムの更改を行った事で、日常生活で2千円札を手にする機会が増え、普及および流通した要因ではないかと推察されます」
たしかに、2022年の衆院財務金融委員会では2千円札が普及しなかったことについて「ATMでの出金に対応していないこと」が一因としてあげられています。しかし、ATMの更改を行っただけでこれほどまでに県民に浸透するものなのでしょうか。
琉球銀行担当者:
「それだけではありません。行政や民間企業などで構成された『二千円札流通促進委員会』を始め、個人で普及活動を行った『二千円札大使』など、県全体で二千円札の普及活動が行われました。こうした官民一体となった取り組みにより一層、沖縄県に2千円札を浸透させることができたのではないでしょうか」

――なるほど、官民一体となった取り組みが2千円札の普及には欠かせなかったのですね。
琉球銀行担当者:
「これらの努力が行われたのは2千円札の表面に首里城へと続く『守礼門』がデザインされていることも大きな要因と考えられます。沖縄県のシンボルがデザインされていることで、沖縄県を象徴する紙幣として認識されているように感じます。沖縄県は『琉球王国』という歴史的な背景や、島という地理的要因も有り、郷土愛の強い県民性が知られています。
直近では、火災で消失した首里城再建プロジェクト稼働等により、さらなる意識醸成が図られているように感じます」
24年前に発行された2千円札が沖縄県で広く普及したのは、沖縄県民の“深い郷土愛”を背景にした官民一体となった取り組みがあったようです。2千円札を手にしたときには、沖縄県の歴史と深い郷土愛に想いを馳せて見てはいかがでしょうか。