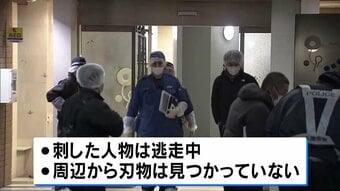なぜ自動音声は女性声なのか、そしてどこへ向かうのか
このように女性の声は社会のなかにあたかも「存在しない」状態として認識されていたが、明治維新以降の教育機会の誕生とそれに伴う職業婦人の登場によって「存在する」ものとして立ち現れた。
その声は電話交換手以外は身体と共に存在したが、逆に電話交換手の登場によって女性の声と身体は切り離され、声のみへのルッキズム的な興味関心が芽生えた。1925年のラジオ放送と女性アナウンサーの登場も、それを拡大し強化していった。しかし、戦争の激化によって女性の声への関心はいったん戦争の背景に隠され、敗戦と共に訪れた新しい社会のなかに再び現れた。
敗戦を経て女性たちが働く場所も拡大し、発する声も大きくなったが、社会のジェンダー規範は以前と大きくは変わっていなかった。高度経済成長に合わせて多くの働き手が必要となり、中学校を卒業したばかりの若者たちが地方から都会の労働力として集団で就職してきた。バス車掌や観光バスガイドもその一つで、多くの若い女性たちが憧れる仕事であった。電話は職場から家庭へと徐々に普及を進め、国家資格となった電話交換手は女性たちの人気の職業であった。
観光バスガイドは、運転手の補助的な役割を担うだけでなく、声で観光客を案内してもてなす職業である。その声は身体と共に存在するが、観光客は目の前にあるバスガイドの身体から声を切り離し、声にのみ注目する。バスガイドに指示された方向を向き、バスガイドが唄う歌に拍手を送る。
観光バスガイドと女性声の関係は、1928(昭和3)年大分県別府市の「亀の井バス」創業者油屋熊八(あぶらや くまはち)が、揃いの制服を着た10代の少女を地獄巡り観光バスにガイドとして乗車させたところから始まっている。彼女たちの観光案内は七五調で行われ、当時の観光客たちは観光地と共に少女たちの可憐な声に魅了された。
その後観光バスガイドは全国の観光地へと拡がり、1935年にはラジオの生中継番組「名所巡り」にも東京の観光バスガイドが「ガイドガール」の名で登場した。彼女たちは新しい女性の職業として注目されたが、そのジェンダー的役割は社会が期待する女性の役割に固定されたままであった。そして、現在において男性のツアーガイドも存在はするが、観光バスガイドは基本的に声の職業であり、女性が担うべき補助的な職業なのである。