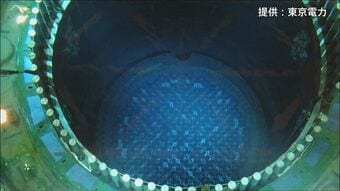「経済環境が許せば9~10月に利上げが意識されるのでは」
日銀は国債の購入減について「相応の規模」になる、そして市場参加者の意見も確認した上、今後1~2年の計画を7月末の次回会合で決定するとしています。末廣さんは日銀がこうして具体的な内容を先送りしたことについて「苦しさが見える」と言います。
「ちゃんと減額していくけど、為替にも国債市場の安定にも金利にも配慮する」というメッセージを「相応」とぼかした表現に込めざるを得ず、5月の金利急上昇以降、一挙手一投足が注目されることで日銀が「つらいコミュニケーション」を強いられている、というのです。
一方、円安を国債の買い入れ減額で直接抑制したい意図が日銀にあるかについては、末廣さんは否定的です。買い入れを減らす狙いについて「長期金利がより自由な形で形成されるように」と日銀が発表していることから、「長期金利は市場で決める、私たちが円安に対応して動かすものではない」という日銀の意図が透けて見えると言います。
住宅ローンの固定金利を決める基準となる長期金利の行方は今後どうなるでしょうか。末廣さんは「これからマーケットとの対話の中でどれぐらい国債買い入れ減額していくか決まるので、しばらく長期金利は上がったり下がったりしやすい」と予想します。
それを受けて、住宅ローン利用者の大半を占める変動金利の基準となる短期金利の追加利上げは、後ろ倒しになる気配です。「7月はまずないかなと思います。国債買い入れの道筋がしっかりついた後、経済環境が許せば9~10月に利上げが意識されるのでは」
利上げが先送りされれば、円安が家計に引き続き重くのしかかります。働く人に景気の実感を聞く5月の景気ウォッチャー調査では、円安による輸入物価の上昇が生活を圧迫しているという声が多く上がりました。ただ末廣さんはどの程度の為替水準が良いかは家計や企業、日銀で違うため、「誰もが納得する為替水準はない」と指摘します。
「インフレを続けたいのなら1ドル160円ぐらいの水準が日銀にとってよいのかもしれない。ただその水準を家計は許せないので、消費マインドは落ちてしまう。日銀は答えがない問題に立ち向かってると言わざるを得ない」と末廣さん。私なら無理です、と笑いながら付け加えて、現在の金融政策の無理難題ぶりに肩をすくめました。
取材協力: 大和証券エクイティ調査部チーフエコノミスト・末廣徹[すえひろ・とおる]