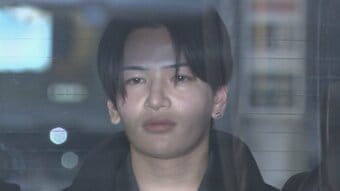長谷川にバトンを託した台本の内容とは?
脚本作りの際、主要キャストをイメージしながら書くことも多いのだが、今回はチーム結成とほぼ同時期に主演が決まっていたのだとか。「モンゴルでの撮影に向かう、成田空港で電話を受けたのでよく覚えています(笑)」と飯田プロデューサー。元々、明墨のキャラクターを俳優・長谷川博己のイメージで作り始めていたが故に、オファー快諾に喜びもひとしおだったという。
「長谷川さんにも明墨のキャラクターについて実際に相談させてもらうことも多々ありました。お芝居をされていく中で、長谷川さんが明墨についてどう感じていらっしゃるのか、その考えを知ることができたのはとても良い経験になりました」と宮本氏。
長谷川は役作りをする上でのニュアンスを、監督やプロデューサーだけでなく脚本家チームにも積極的に聞いていたという。山本氏は、「セリフについてではなく、明墨だったらここは笑うのかなとか、動かずにやった方がいいのかなとか。実際の法廷見学もご一緒させていただきましたが、弁護士先生の物理的な立ち位置を考えながらご覧になっている姿が印象的でしね」と明かす。
「私たちも実際にお話を聞いたり、演じられた明墨の姿を見たりして、これは長谷川さんにお任せしたいという気持ちが強くなりました。なので、明墨がどういう感情なのかを台本上では明確にせず、放送や撮影を観て驚く。まさに視聴者の皆さんと同じ気持ちです」と続けながら、山本氏は台本作りの舞台裏を鮮明に語ってくれた。

4人と飯田プロデューサーのアイディアを集結させたからこそより繊細な台本に仕上がっているわけだが、飯田プロデューサーは世間で認識されている“考察系ドラマ”という位置付けについて、ある思いを抱えていると言う。「考察系を狙っているわけではないんです。法律モノなので入り組んで複雑化してしまう部分は確かにありますが、全話を通して観たときに“なるほど、そういうことか”と感じてもらえたらいいと思っています。4人でアイディアを出し合って、緻密に作ろうとした結果が“考察系”という認識に繋がっているのではないか」と、本音を吐露。
日本ではまだ珍しい“共同脚本”というシステムだが、新たな可能性という意味ではエンターテインメント界の今後を左右する大きなチャレンジだ。“共同脚本”は、そもそも話し合いに多くの時間を割かなければいけない上に、まとめる人間は常に選択を迫られる。しかし、時間を掛けることができるのであればそれは決して不可能ではないはず。近い将来、日本のドラマや映画、舞台など、様々な作品で“共同脚本”という文言を目にする機会が増えるかもしれない。