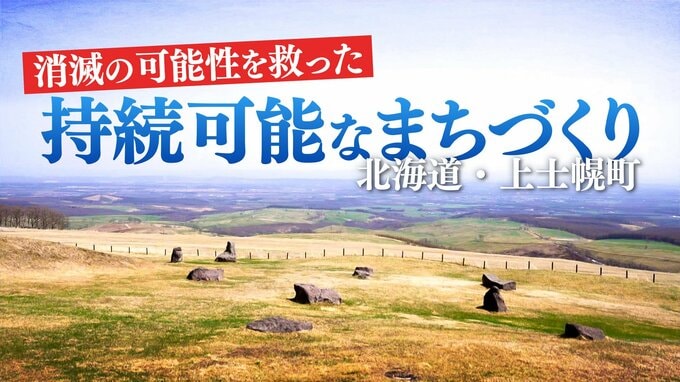少子化や人口流出に歯止めがかからず、消滅するかもしれないとされた北海道の小さな町では、最先端技術を駆使して地域の魅力を伝えることで若い移住者が増えている。そこは早くからSDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいる町としても知られていた。

2014年、「消滅する可能性がある自治体」とされた町は今‐。
東京から移住 島田裕子さん(32)
「常に新しいことをやり続けている。すごく刺激的な町と思っています」
東京から移住 菊池拓海さん(26)
「広い土地があって人口5000人弱なのに移住者が多い。私は全然まだまだ消えない町と感じています」
背景には、未来を見据えた“持続可能なまちづくり”があった。
小さな町の生活を豊かにする最先端技術「きょうの新聞がきょう届くように」

北海道・十勝地方最北部に位置する上士幌町。廃線となった旧国鉄士幌線のアーチ橋「タウシュベツ川橋梁」や日本一広い公共牧場「ナイタイ高原牧場」などの観光地があり、大自然に囲まれた広大な土地を生かして行う畜産や農業が盛んな町だ。
緑豊かな町内を走るバスには‐。

田中優衣 記者
「ハンドルを操作する運転手がいないですね」
自動運転バスの運行だ。車内には対話可能なAI車掌を全国で初導入。2024年5月には、一定の条件下で無人運転を行う「レベル4」での走行が道内で初めて認可された。いまは安全を確認するオペレーターが乗車しているが、将来的には完全な無人運転やルートの拡充を目指している。
さらに、ドローンの配送事業も行う。これも日本初の取り組みだ。

新聞を受け取った人
「この辺1日遅れの新聞配達だったが、きょうの新聞がきょう届くようになって便利になりました」
ICT(情報通信技術)の活用に力を入れている。人手不足の解消と脱炭素を両立した持続可能な地域交通の確保に向け、これからも取り組みを進めていく考えだ。
そして、特に注力する分野が資源循環型農業とバイオガス発電の地産地消。町には大規模な酪農事業者が多く、事業拡大による牛の増頭増産に伴いふん尿の適正な処理が課題となっていた。実際、2024年6月時点で、人口の8倍近い3万7000頭の牛が飼育されている。

ドリームヒル・環境部バイオ課 宗像勇輔課長
「大量にいる牛から出てくるふん尿を使って発酵させてガスを燃やして発電機を動かす」
牛から出るふん尿を40度で40日間ゆっくり発酵させるとバイオガスが発生。そのガスを燃やして発電機を動かすことで電力になる。これがバイオガス発電だ。
作られた電力はいったん北海道電力に売電され、この売られた電力を町の観光地域商社「karch」がもう一度買い戻し、小売事業者「かみしほろ電力」が町内の一般家庭や公共施設などへ電気として供給。“町で作った電気を町で消費する”仕組みを作ったのだ。今後、町全体をカバーできるくらい発電したいとしている。
さらに、発電に使われたふん尿は発酵後、固体と液体という形で残ってしまうが、固体は牛の寝床に敷く「寝わら」に。液体は畑にまく「肥料」として再利用される。牛のふん尿を余すことなく使い循環させる、このサイクルが資源循環型農業の流れだ。