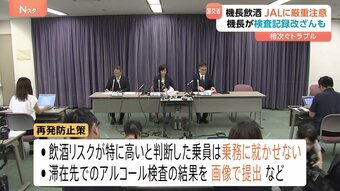オレンジから“国産みかん”にシフトも課題が…
では“国産みかん”はというと、立ちはだかるハードルが二つあります。
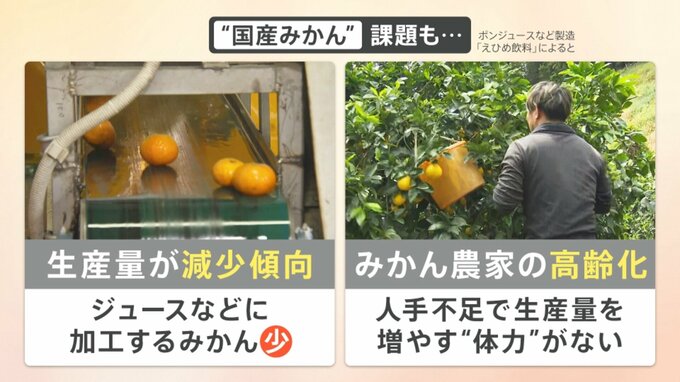
▼生産量が減少傾向
高級なみかんを作るということにシフトする生産者が多く、ジュースなどに加工する安いみかんが少ない現状
▼みかん農家も高齢化
人手不足で生産量を増やす“体力”がない
「オレンジが駄目なら、みかんがいい」ということでみかん農家が喜んでいるかというと、生産量が減少傾向にあるのでみかんにもシフトできない、というところが見えてきます。
ホラン千秋キャスター:
私達の身近な食品がいろんなピンチに面していますが、目先のピンチだけではなく長期的に考えると、様々なものが生産しづらくなっている。気候が変わってきていて、生産するものを変えなければならない、など広い目で見るとかなり大きな問題だと伝わってきます。
スポーツ心理学者(博士) 田中ウルヴェ京さん:
広い目で見ると、いかに環境の変化が生産物に影響するのか、ということをまずは自覚せざるを得ない、ということ。需要と供給のバランスは、簡単に私達がどうかできるものではないので、みかん生産者の人たちが一時大変になる可能性は当然ありますが、上手に生産者の皆さんを支援しながら、少しずつみんなが食べていければいいな、とは思います。
ホランキャスター:
これまでオレンジジュースを加工していた業者などは、「空いてしまった分は何で埋めるか」など課題があるわけですよね。
井上キャスター:
今回はオレンジジュースに焦点を絞りましたが、これまで日本は「1ドル100円ぐらいをベースに輸入で頼っていこう」としていたので、これから自給自足を考えなければいけないのか。「こういったリスクはつきまとう」ということも突きつけられますよね。
田中ウルヴェ京さん:
やはり、急激な円安・急激な円高、そういうことが輸入にはとても影響があるので、そこはもちろん考えていかなければいけないところですね。
==========
<プロフィール>
田中ウルヴェ京 さん
スポーツ心理学者(博士)
五輪メダリスト
慶應義塾大学特任准教授
アスリートの学び場「iMiA(イミア)」主宰