■避難所の発電機は「わずか2人分」
一方で、大きな課題も見つかりました。医療機器が欠かせない障害児にとって、電源が確保できるかどうかは、命に直結する課題です。しかし……。
笠間さん「湯たんぽとか、電気毛布で保温するのも、お湯を沸かすのも全部電気。1つの発電機で2人が限界かも」

避難所にある発電機では、医療的ケア児の医療機器が2人分しかまかなえないこともわかりました。
笠間さん「一言でいうならやってよかった。実践じゃないと見えないことっていっぱいあるので。今回もガソリンタイプの発電機でも、医ケア児1人か2人入れられるかどうかというところまで計算できた」
■当事者では限界も「存在を知ってほしい」
こうした課題を多くの人に知ってもらおうと、笠間さんたちは今月11日、講演会を開きました。

本田医師「私たちが目指すのは、医療的ケア児の震災対策に取り組むことで、いわき市に住む多くの関係者の方々の考え方が変わることを目指したいと思う」
災害弱者の避難では、当事者の努力だけでは限りがあり、登壇した人たちは地域の住民の協力が不可欠だと訴えます。
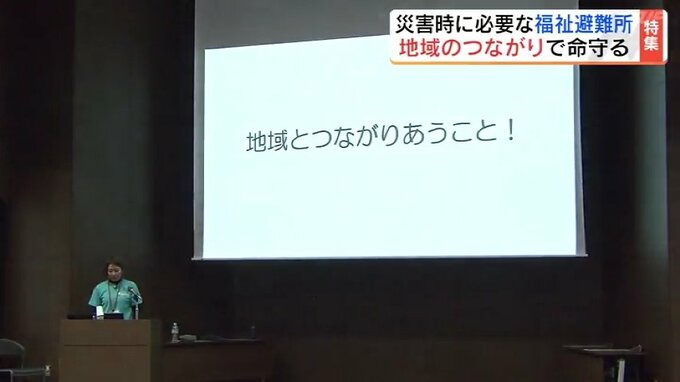
笠間さん「私がきょうみなさんに、覚えていってほしいことはここです。地域とつながり合うこと!」
自分の地域に、重症児がいること。それを知ってほしいと、会場で理恩さんとともに訴えました。
「存在を知ってもらうことが基本の『き』『助けて』と子どもたちは自分で言えないんですよね。声は出ても言葉としては『助けて』とはなかなか言えない子どもたちなので」
■私たちは子どもたちを守る「仲間」

2019年の台風19号で一時、孤立した経験から、町内会の活動に参加するなど、地域との関わりを積極的に持つようになった笠間さん。最後に集まったおよそ100人を前に、呼びかけました。
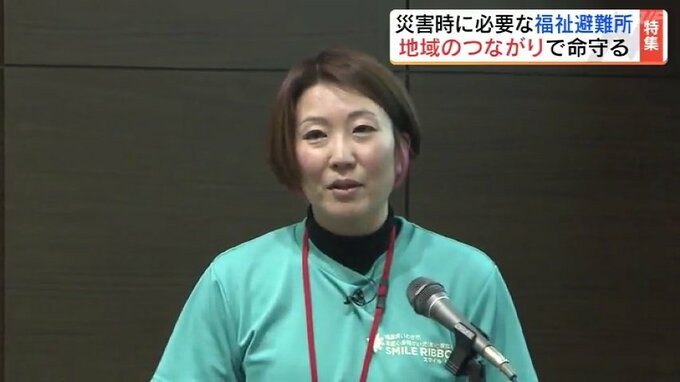
「きょう参加いただいたみなさんは、もう障害児の生活なんて、障害児の避難なんてわからないとは言わせません。積み上げてきたことが武器になります。私たちは一緒に地域を守り、子どもたちを守り、育て、次の世代につないでいく仲間です」
少しずつ動き始めた災害弱者を守るための動き。いざという時、自分たちに何ができるのか。地域を守る「仲間」と呼びかけられた私たちが考える番です。














