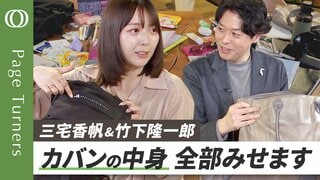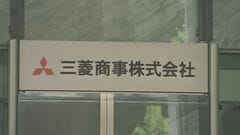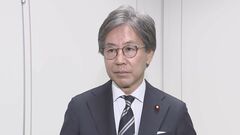(ブルームバーグ):台湾有事を巡る高市早苗首相の発言に反発した中国は、ここ約3週間で経済的報復や対日批判、外交圧力を相次ぎ繰り出し、不快感をあらわにしてきた。
足元では国連でこの問題を取り上げ、対立をさらにエスカレートさせている。台湾を巡り衝突が生じた場合に中国を支持するか、あるいは干渉しないよう各国に圧力をかける狙いがある。
中国の傅聡・国連大使は21日、国連のグテレス事務総長宛ての書簡で、高市首相の発言が国際法に違反していると非難。「日本が台湾海峡を巡り軍事介入すれば、それは侵略行為となる」と述べ、「中国は国連憲章および国際法の下で自衛権を断固として行使し、国家主権と領土の一体性を守る」と強調した。
この書簡によって、グローバルサウス(新興・途上国)を中心に中国が広い支持を集める国際機関の場に、日中間の対立が持ち込まれた格好だ。自衛権の行使を持ち出すとともに、日本の介入を侵略行為と位置づけることで、中国は実質的に米国を含むいかなる国・地域も有事に台湾防衛に加わるべきではないとの主張を展開している。

国際危機グループの北東アジア上級アナリスト、ウィリアム・ヤン氏は書簡について、中国が将来、軍事行動に踏み切る際の「法的根拠や論理構築を進める新たな取り組みの第一歩となる可能性がある」と指摘。これには紛争時に日本の資産を攻撃対象とすることも含まれると述べた。
バイデン前米大統領は中国が侵攻すれば米国は台湾を防衛すると繰り返し表明していたが、米国が「深刻な痛みを与えられる」ことを中国は理解しており、慎重に対応していたと同氏は指摘。これに対し、中国経済への依存度が高い日本は標的として狙いやすいという。
中国は「トランプ政権が日本にどの程度、具体的な支援を提供する意思があるのかを見極めようとしている」とヤン氏。また「台湾を巡って同様の発言をすればどうなるのか、他の民主主義国に警告しようとしている」と続けた。
中国による国連への書簡は、日中対立問題を巡り国際社会の支持を集める狙いがある。加盟国の投票を要する正式な決議ではないものの、この問題に対する立場について検討するよう各国に迫っており、それだけでも中国にとっては十分な成果となり得る。
ナティクシスのアジア太平洋チーフエコノミストで、国連における中国の影響力を研究してきたアリシア・ガルシア・エレロ氏は「中国にとって必要なのは沈黙だけだ。沈黙は黙認であり、受け入れを意味する」と指摘。「誰も常軌を逸しているとは発言しておらず、中国にとってこれはすでに大きな勝利なのだ」と語った。
高市氏への激しい批判の中で、中国当局者や国営メディアの論評は折に触れ、日本がかつて中国や他のアジア諸国に対して行った戦時中の侵略を引き合いに出し、高市政権が「軍国主義」という危険な道に回帰していると非難している。
21日には、在日本中国大使館がSNS「X(旧ツイッター)」への投稿で、日本が再び侵略に踏み出すような行動を取った場合、中国には国連安全保障理事会の承認を得ずに「直接的な軍事行動」を取る権利があると主張。第2次世界大戦中の「敵国条項」に関する国連憲章の規定を根拠に挙げたが、詳細な説明はなかった。
日本政府は敵国条項については1995年の国連総会において、死文化しているとの認識を示す決議が圧倒的多数の賛成により採択され、中国自身も賛成票を投じたと指摘。小林麻紀内閣広報官は国連安保理常任理事国である中国が大国として責任ある言動をとるよう期待したいと述べた。
「静観するのが得策」
中国はこれまで、ロシアによるウクライナ侵攻と台湾問題の比較を一貫して退けてきた。その根拠として、ウクライナは主権国家だが、台湾は中国の一部であり問題は内政だとの主張を展開。ウクライナの国境は尊重しながら、台湾に対しては中国の主権を侵しているとして、米国やその同盟国が「二重基準」を取っていると批判している。
高市氏を非難する中国に同調したのはロシアなどごく少数で、他の多くの国は静観の構えを示している。主要国で日本への支持を表明したのは米国のみで、日本の防衛に対する米国の責務は揺るぎないと述べている。
中国政府が高市氏を執拗に攻撃するのは、国内向けの政治的な狙いもある。歴史問題を抱える日本に対して一歩も譲らない姿勢を示すことで、習主席を強い指導者として印象づける意図があるとみられる。
アトランティック・カウンシルのグローバル・チャイナ・ハブの非常勤フェロー、宋文笛氏は、中国が日本との対立を通じて国内のナショナリズムを高めると同時に、他国が台湾問題で発言することを抑止する狙いがあると話す。
「国連の場で他国に中国への支持を表明させることで、数の力によって自らの立場の正当性を示そうとしている」と同氏。「2つの経済大国が争う状況では、おとなしく静観するのが得策だ」と語った。
原題:China Uses Japan Spat to Pressure World to Pick Sides on Taiwan(抜粋)
(第10段落目に中国の動きを加え、見だしを更新します)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.