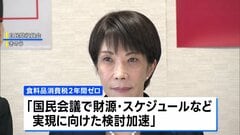注目点
USD/JPYは10月の金融政策決定会合後に水準を切り上げ、153~154円台で推移しているが、一方的な円安は回避されている。その理由として政府・日銀の為替介入に対する警戒感があろう。
事実、三村財務官は11月5日に「為替の実際の動きと日米の国債の金利差の推移を見ると、最近はやや乖離が見られると言える」、「基本的にわれわれは常日頃から米国債と日本国債の金利差に着目すべきだと言っている」と、為替介入の用意があることを仄めかすような言及をしている。
2022年以降の円安局面では、大きく分けて2度の介入実績があり、2022年9~10月はUSD/JPY150円、2024年4~7月は160円の攻防であった。次の為替介入はどれくらいの水準になるだろうか。
「特定の為替水準を目標にしない」という原則を重視すれば、155円近傍での介入は憚られることになろう。155~160円水準における2度目の為替介入はこの原則に抵触する恐れがある。
ただし、ここで言う「特定の為替水準」は、輸出競争力強化を狙う通貨安競争の防止を念頭に置いていることに留意する必要があろう。
したがって、日本政府の円買い介入を受けて他国から批判が噴出するとは考えにくい。この点において為替の水準条件はさほど問題にならないだろう。
ファンダメンタルズから急速に乖離するような動きを是正するための為替介入はあり得るだろう。
三村財務官も言及したように、2025年入り後の円安は日米金利差(或いは米金利単独)に逆行して進んでおり、これを「ファンダメンタルズで説明できない投機的な動き」と見做すことは比較的容易である。
2025年入り後、日本の10年金利が大まかに0.5%上昇、米10年金利が0.5%低下したにもかかわらず、円高には至っていない。
筆者は日米金利差の説明力が衰えている背景に貿易・サービス収支の赤字体質があると判断しており、概ねファンダメンタルズに沿った動きと解釈しているが、為替介入の表向きの理由として「日米金利差に逆行する円安」は、それなりの妥当性がある。
この点においてUSD/JPYが155~160円で推移する中での為替介入はあり得る。
また日米の財務当局者の見解も重要であろう。ベッセント財務長官は、金融政策決定会合の直前である10月29日にSNSで「日本政府が日銀に政策余地を与える姿勢は、インフレ期待を安定させ、過度な為替レートの変動を回避する鍵となるだろう」と投稿。
高市政権が日銀の金融政策に介入しなければ、日銀が利上げを決定することで円安を止めることが可能であると読み替えることができる。円高を促す意図が透けて見える。
日本では、片山さつき氏が5月に「USD/JPYは120円台の時期が長かったので、120円から130円、120円台が実力との見方が多い」としたほか、財務相就任後の11月4日には最近の円安について「一方的で、急激な動きがみられている」と警戒感を滲ませている。
日銀の利上げ見送りによって加速した円安を為替介入で抑え込むことの妥当性を米国側にどう説明するかは微妙であるが、日米財務省トップの考え方は大枠で一致しているように映る。
以上を踏まえると、USD/JPYが155円を突破してくるようだと日本政府による為替介入の可能性が高まると判断される。また日銀が12月会合における利上げを示唆する可能性も高まってこよう。
※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 藤代 宏一