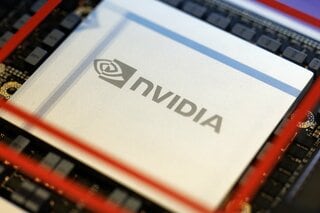まとめ
ここまで見てきたように、潜在成長率は経済の供給力を示す概念とされるが、推計方法や推計に用いるデータに大きく依存する推計値であり、実際には需要面から決まる要素が多い現実のGDP成長率と強く連動する。
シミュレーション分析では、2027年度末まで2%成長が持続した場合には潜在成長率が1%台前半まで上昇する一方、ゼロ成長が継続すれば潜在成長率もゼロ近傍に低下することが示された。
成長力の強化には供給サイドの改革のみならず、需要の継続的な拡大が不可欠である。
日本経済を需要面からみると、近年の日本経済の停滞は家計消費と設備投資の低迷に起因しているが、家計消費は実質可処分所得の伸び悩み、設備投資は企業の投資性向の低下により抑制されている。
家計部門では名目所得の増加が実質増税につながる「ブラケットクリープ」により可処分所得が下押しされている。
インフレに対応した税制の見直しなどで実質可処分所得を恒常的に増やすことによって、消費を喚起することが、設備投資の増加や潜在成長率の押し上げにもつながるだろう。
現在の潜在成長率はあくまでも過去の日本経済を定量的に捉えたものであり、現時点の潜在成長率を所与のものとして日本経済の将来を考える必要はない。
需要の拡大を通じて現実の成長率を高めることが、日本経済が長期停滞から脱するための鍵となるだろう。
※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎
※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。