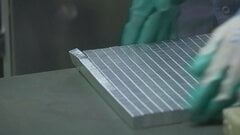国際協力銀行の出資、融資、融資保証が中心
では、どのような形で金融支援を行うのでしょうか。トランプ大統領が案件を決めると、そのプロジェクトを管理・統治する特別目的事業体(SPV)が設立されます。その上で、プロジェクト単位のSPVに対し、政府系金融機関である日本の国際協力銀行(JBIC)が、出資したり、融資したり、さらには融資保証を行います。融資保証とは、日本の民間銀行などが、このSPVに融資した場合に国際協力銀行が保証を行うという意味です。
SPV、つまりそのプロジェクトがうまく進めば、融資は返済され、その間の貸付利子がJBICや邦銀に入ります。プロジェクトが順調なら、コストを上回る利益も出ます。
利益は、融資が返済されるまでは、日米が50%ずつ、融資返済後は日本が10%、米国90%で分配するとしています。利益配分1対9の算定根拠は明記されていませんが、赤沢大臣のこれまでの説明からすると、JBICの出資比率が10%程度に留まることを前提にしているようです。
経済安保促進の観点も
プロジェクトの対象として、半導体、医薬品、金属・重要鉱物、造船、パイプラインを含むエネルギー、AI、量子コンピューティングが、具体的に覚書に挙げられており、経済安全保障に焦点を当てています。
生産施設などの立地がアメリカだとしても、それが米経済のみならず、日本の経済安全保障にも貢献するのであれば、日本が資金を出す意味があるという考え方なのでしょう。その意味で、今回の合意は、経済安保という新しい時代のニーズも踏まえた、新しい経済協力の在り方を示した面もあると言えるかもしれません。
焦げ付きは国民負担のリスク
しかし、結果的にプロジェクトがうまく行かないケースも、想定しておく必要があるでしょう。プロジェクトが失敗すれば、利益の分配どころか、日本側が拠出した出資や融資が焦げ付くリスクがあることは明白です。
とりわけトランプ大統領が、経済合理性よりも政治的アピールを狙って、短期間に次々とプロジェクトを決めれば、なおさらです。その際には、融資保証した分も含めて、国際協力銀行が焦げ付きを被ることになるのです。
国際協力銀行の資金の原資は、財政投融資。郵便貯金や年金の資金が間接的に投入されているのですから、焦げ付きは、最後は、日本国民の負担になってしまいます。そのリスクにさらされるのが、総額80兆円ということになります。果たして、石破政権は、最悪の事態を想定した覚悟があって、この覚書に署名したのでしょうか。