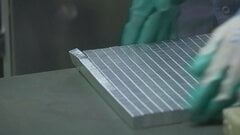「安過ぎる」と言われた落札価格
三菱商事が落札した価格は、1キロワット時あたり、秋田県能代市沖が13.26円、由利本荘沖が11.99円、難工事が予想される千葉県銚子市沖でも16.49円で、上限価格とされた29円の半額程度、あるいはそれ以下でした。競合企業からは、20円近くでないと採算は取れないはずで、三菱商事の示した価格では採算割れになるのではないかという危惧の声も聞かれました。
洋上風力発電事業を主要事業にするために、かなり無理をした入札価格を出したのではないかという指摘は、今回の問題の1つの要因と言えそうです。
インフレの影響を受ける長期プロジェクト
しかし、それ以上に大きな要因は、インフレ時代になって、資材価格も、作業員の人件費も、そして金利も大きくあがり、建設コストが2倍にもなったことでしょう。インフレ時代への移行が、こうした長期大型投資の見通しを困難にしているという事実です。
三菱商事が撤退した後、入札第一号だった3海域に、代わって参入する企業が出てくるのかが、当面の大きな焦点です。また、すでに落札企業が決まっている入札第2号(秋田・新潟・長崎県沖の4海域)や第3号(青森・山形県沖の2海域)から、三菱商事と同じように撤退する企業が現れはしないか、関係者は固唾を飲んで見守っています。さらに北海道沖など、今後の入札計画がどうなるのか、その先行きは不透明です。
洋上風力発電事業の制度見直しも必要
再生エネルギー促進のために、風力発電で発電された電気は、原則20年間、固定価格で電力会社に買い取られることになっています。こうした仕組みにすることで、事業主体は20年間の安定した収入を見通し、事業計画を立てやすくしているわけです。しかし、コストが増大する中で、20年という期間では投資回収には短過ぎるというケースがあるかもしれません。また元々、事業者にメリットが大きかった固定価格での買取が、インフレ時代には逆に値上げできないリスクになる場合もあるかもしれません。
今の制度の基本的な枠組みが作られたのが、デフレ時代であることを考えると、今回の三菱商事撤退を機に、洋上風力発電をめぐる入札制の制度的課題を洗い出し、必要な見直しを行うことが必要です。