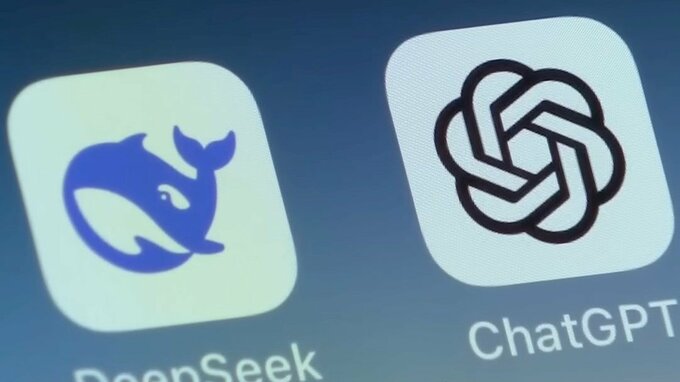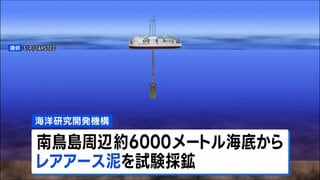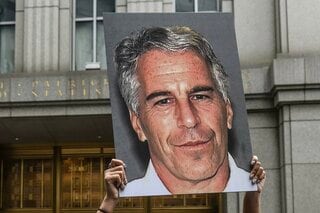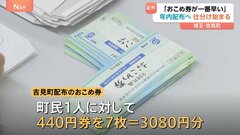近年、調査や研究の現場においても、生成AIの活用が急速に広がっている。
壁打ちツールとして自身の思考を深めたり、要点を整理したりするだけでなく、これまで視野の外にあった論点や視座に気づかされる場面も増えてきた。
一方で、生成AIが出力する情報の真偽を確認し、事実関係を検証するために相応の時間を費やすことになり、本当に「効率化」と呼べるのか、疑問を感じる場面も少なくない。
こうした体験のなかで思い至ったのが、「生成AIとは情報のデリバティブ(派生物)である」という比喩である。
金融分野の人間からすると、生成AIの構造を金融商品に例えると理解が深まる場面が多い。この構造は、金融の世界における「デリバティブ(金融派生商品)」と非常によく似ている。
デリバティブの構造と役割
金融における「デリバティブ」とは、株式や債券、金利、為替、原油などの「原資産」の価格や変動性に連動するよう設計された金融商品を指す。先物取引やオプション、スワップなどがその代表格である。
たとえば、将来の金利上昇リスクに備える企業が金利スワップを用いる場合、それは「金利」という原資産の動きに基づいて損益が決まる商品を売買していることになる。
デリバティブそれ自体は直接的な価値を持たず、あくまで基盤となる原資産の動きに依存して価値が形成される。ゆえに「派生商品」と呼ばれ、原資産との連動性が確保されてはじめて合理的な意味を持つ。
生成AIと情報の派生性
生成AIもまた、事実そのものを直接提供しているわけではない。学習した過去の文献や公開情報、インターネット上の文章などをもとに、統計的な傾向を捉え、「もっともらしい出力」を構成して提示している。
したがって、生成AIが生み出す回答や文章は、それ自体が情報の「原資産」ではなく、過去の情報に基づいて構成された派生物である。
重要なのは、ここで言う「原資産」がいわゆる一次情報(観察、取材、統計データ等の未加工情報)だけではなく、二次情報(解説記事、要約、報道)や三次情報(SNSの感想、AIの出力内容など)も含まれている可能性があるという点である。
学習の過程で、これら異なる層の情報が区別されるわけではない。したがって、生成AIは「一次情報のデリバティブ」というよりも、膨大な情報群を圧縮し再構成した「複合的デリバティブ」と見るほうが妥当であろう。