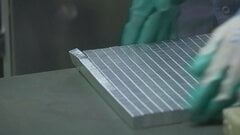「売れる車がない」から脱却できるか
250万台の生産でも採算がとれるようにするというリストラは、最初の一歩に過ぎません。リストラしただけで、販売店が「売れる車がない」と嘆く状況が急に改善するわけではありません。
新型のエルグランドやリーフなど今後投入される車がどれだけ支持を集め、さらにそれに続く魅力的な新型車が投入できるかどうかが、再起に向けた今後のカギになります。
その上で必要なことが、クルマがかわる将来への投資です。
日産・ホンダが基盤ソフト共通化へ
こうした中で14日、日産とホンダが、自動車を高度に制御する基盤ソフトウエアを共通化する方向で調整に入ったことが明らかになりました。基盤ソフトウエアは、自動運転やライドシェア、車内でエンタメなどの機能を拡張するための中心となる技術で、SDV(ソフトウエア・デファインド・ビークル)の基盤となるものです。
SDVでは、この基盤ソフトウエアが更新されることによって、車の機能が随時、より進化、高度化する仕組みです。自動車会社のビジネスモデルを、これまでの「車の売り切り」から、ソフトウエア更新による継続課金(サブスク)へと、大きく変化させることになります。
基盤ソフトウエアの開発には、巨額の投資が必要なことから、いったん経営統合協議を打ち切った日産とホンダが協力する方向になったものです。小さくなった日産が将来への投資を続けるためには、ホンダや自動車企業に限らず、外部との幅広い協業が必要です。
外部との協業で将来投資
クルマの未来像がなかなか1つに絞れない中、トヨタのように、ハードもソフトも、EVもハイブリッドも水素車もと、フルライン、全方位で開発が進められない中、日産が「勝ち筋」を見つけるためには、お得意の「内向き」志向から、「外に開かれた企業」に変わることが欠かせません。
ホンダとの経営統合が破綻した今は、将来のために必要な投資は、具体的な項目ごとに協業相手を見つけていく以外、当面、道はありません。
再起をかけた、いわば最後の戦いは始まったばかりで、エスピノーサ社長をはじめとする現経営陣の肩には、その重い責任がかかっています。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)