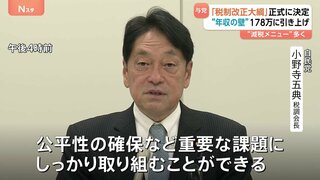介護職員等による高齢者虐待防止に向けて
厚生労働省は、調査結果の公表と同日、各種養介護施設の取りまとめ団体宛て、「高齢者施設等における高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のための措置の徹底並びに周知に関する取組の実施について」との要請文を発信している。
そこには、主に以下のような周知徹底事項が記載されている。
2024年4月1日から、全ての介護サービス事業者を対象として高齢者虐待防止措置(委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の実施、担当者を置くこと)の実施が義務づけられており、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合には、基本報酬が減算されること。
2024年4月1日から、訪問・通所系介護サービス等に対し、身体的拘束等 の原則禁止と身体的拘束等を行う場合の記録が義務づけられていること。
委員会での検討事項と、参照すべき厚生労働省からの通知や研修資料、また、今年度末までに自治体向け「高齢者虐待対応マニュアル」を改訂予定であることも記載されている。
こうした事項は、各養介護施設が自らを律し、高齢者虐待を防止するための手法を提供するものとして有効であることに異論はない。確実な遂行が求められる。
しかし、行政は、養介護施設がこうした手法を確実かつ効果的に実施するためには相応のリソースが必要であることを常に念頭に置く必要がある。
日々、養介護施設で高齢者に接しているのは介護職員等であり、その中で発生する高齢者虐待を防止するためには、枠組みや材料に習熟し使いこなす十分な数の介護職員等の存在が不可欠である。
さらにいえば、養介護事業所を監督・指導する自治体のリソースも重要である。
国が発するさまざまな指針やマニュアル類を養介護事業所に適切に理解・運用させ、不適切な事象が発生した場合の原因究明・再発防止を指導・モニタリングするに足る人員が必要である。
養介護施設における高齢者虐待は、図表2が示す通り、多種多様な原因が絡み合って発生するため、必ずしも十分な介護職員等がいれば根絶できるものではないものの、介護職員等や自治体職員の適切な配置は最低限必要な要素であると考える。
介護職員等の確保については、国もさまざまな施策に取り組んできたが、具体的な成果にはつながっておらず、今後大幅な介護職員等の不足が認識されているなかで、2023年度の介護職員数は介護保険創設以来はじめて減少に転じた。
こうした状況下、2024年度の介護保険制度の見直しでは、介護職員等の処遇改善に向けて処遇改善加算の仕組みが改善され、加算率も引き上げられたが、目指すベースアップの水準が2024年度に2.5%、2025年度に2.0%であり、おおむね他の業種に大きく劣後し、物価上昇にも追い付かない。
2025年度の日本労働組合総連合会「春季生活闘争方針(春闘方針)が賃上げ5%以上(中小企業6%以上)と決定され、UAゼンセンはパートタイマーの賃上げ7%基準を要求する方針であるなかで、人材獲得競争における相対的劣位がさらに顕著になる。
公益財団法人介護労働安定センターの調査によると、仕事の満足度D.I.(「満足」と「やや満足」の合計と「不満足」と「やや不満足」の合計の差)でみると、「賃金」はマイナス18.0ポイントで最も不満度が高く、賃金への不満が顕著に表れている。
前述のとおり、賃金の低さは介護職員等の大きなストレスにもつながっている。
こうした状況を大幅に改善しなければ、他にどのような手を打っても介護職員等の確保は難しいと考える。
厚生労働省は、介護職員等の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価について、2025年10月に調査を行い、2026年3月頃に公表する予定である。
現行制度では、処遇加算の仕組みが改善され、加算取得のための事務負荷が軽減されているという。
介護職員等の処遇改善状況を精査したうえで、必要な追加措置がとられることを期待する。
介護施設における高齢者虐待を防ぐための具体的な手法は、今後も好事例やマニュアルなどで示されるだろう。
それを確実に実践するには、介護職員等の賃金を大幅に引き上げてその魅力の向上を実現し、現場で仕事に対する高い満足度をもって活躍する必要十分な数の介護職員等を確保することが最重要であると考える。
今後、高齢者介護は選択の余地なく一層の対応が迫られる。高齢者虐待防止も含め、適切な高齢者介護の環境整備に向けて、迅速かつ思い切った資源投下を行う必要があると考える。
※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承くださいませ
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所)