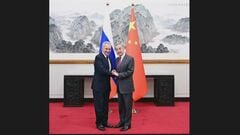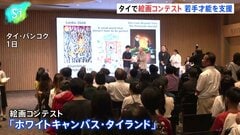ブリリアント・ジャーク(Brilliant Jerk)とは
ブリリアント・ジャークとは、「優秀で仕事はできるが、言動にトゲがあり、周囲に悪影響を与える、協調性の無い人材」のことを指し、「優秀(=Brilliant)」と「嫌なヤツ(=Jerk)」を組み合わせた造語である。
米国の某世界的動画配信企業(以下、某社)が自社の採用サイトで、「ブリリアント・ジャークは受け入れない(不採用、もしくは解雇する)」として挙げたことで、一躍有名な言葉となった。
ことITの世界では「優秀な人材は普通の人材よりも1,000倍価値がある」とも言われており、多くの学術的な研究でも、いわゆる優秀なパフォーマーは彼らの同僚よりも何倍も生産性が高く(Cole and Cole, 1973; Ernst, Leptien, and Vitt, 2000; Narin and Breitzman,1995)、特に知識労働においては、彼らの能力と経験は、その他のパフォーマーや非人的資源では補うことができない資産である(Narin, 1993; Rosen, 1981)ことが明らかにされている。
にも関わらず、某社は自社に必要な人材は、「優秀な人材で且つチームプレーヤー」であり、協調性の無いブリリアント・ジャークは「容認する会社はあるが、我々にとって、効果的なチームワークを維持するためのコストが高すぎる(Some companies tolerate them. For us, cost to effective teamwork is too high.)」として、まず採用時点で排除し、採用してしまった場合には「勇気をもって解雇する」としているのだ。
なぜ「チームワーク」が必要なのか
前段の某社が、欲しい人材として「チームプレーヤー」を挙げているように、日本でも多くの企業が「最も重要と考える能力・スキル」に「チームワーク、協調性、周囲との協働力」といったチームプレーヤーとしての能力を挙げている。
たとえチームワークが無くとも優秀な人材さえ揃えば、高い成果を上げられるのではないかと考える人もいると思うが果たしてそうなのか。次に、これを調査した米国の研究成果を見てみる。
ウォール街の投資銀行に所属する799名のエクイティアナリストと254名の債券アナリストの離職率と転職前後のパフォーマンスを9年間にわたり調査した研究がある(B.Groysberg, et al.、 2008)。
研究対象となったアナリストは、機関投資家(投資運用会社、州の年金基金等)の評価をもとに毎年発表されるランキングの上位に入る、いわゆる「スターパフォーマー」と呼ばれる人材である。
アナリストのスキルは、組織のサポートを超え、個人の能力に起因するとされている(Howard, 1967; Lurie, 1967; Institutional Investor, 1991)ため、労働市場では非常に転職しやすい職種だと認識されている。
また、新しい企業に転職した後でも、アナリストは同じ財務モデルを実行し、同じ企業を追い、同じ顧客リストを維持し続ける(機関投資家は特定の投資銀行と排他的な関係を持っているわけではなく、同時に多数の銀行からリサーチレポートを受け取っている)ことから、転職前後のパフォーマンスを比較しやすいとされている。
当該調査対象のアナリストは、より条件のよい競合他社へ毎年平均11.9%が転職しているものの、転職先での業績は元の職場より低下する傾向にあり、転職による低下効果は最低5年継続するという結果が明らかとなった。
一方で、転職先でも業績の下がらなかった人たちが一部存在し、その要因を調査したところ、その人たちは個人ではなく「チーム全体」で転職していたことがわかった。
アナリストの仕事は、その職務の特性上、また個人でランキングされることからも推察されるように、一見すると、個人の高い能力のみが必要とされると思われがちである。
しかし実際は、異なる。アナリストに限らず個人プレーが多いと思われる職務であっても、同僚のチーム間の協力が重要であり、そのチームワークが機能した結果、より高い成果を出すことができているといえるだろう。