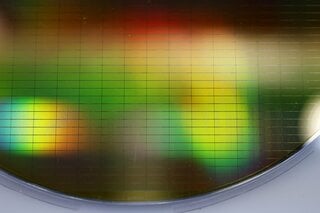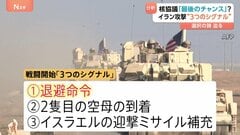特定の園を希望するのはわがままなのか?
隠れ待機児童の内訳で最も多いのは「類型(2)特定の保育園等のみ希望している者」で、過半数を占めている。
「特定の保育園」をどう判断するかは自治体によって異なるが、自宅から一定の距離内の保育園に空きがある場合、特定の保育園を希望しているとみなす基準が多くみられる。
一定の距離とは通常の交通手段により自宅から20〜30分未満が目安の一つとなっている。
たとえば、徒歩で20〜30分、自転車だと10〜15分程度のケースで、毎日通園にかかる負担を考えてみる。
首都圏は地価が高いこともあり、保育園は駅周辺とは限らない。最寄り駅と反対側の場合、いったん子どもを送り、また駅に向かって出勤するケースもあるだろう。
迎えに行く場合も同様の負荷がかかる。
さらに、兄弟姉妹が別園の場合はいっそう送迎に時間と手間がかかる。
こうした毎日の負担は業務時間を圧迫する。
通園しやすい特定の保育園を選ぶことは、仕事と育児の両立と業務パフォーマンス向上に直結するのである。
さらに、希望した子どもの数をあきらめる要因にもなりうる。
また、一度認可保育園に入園すると転園は容易ではないため、いったん入園して希望園の空きを待てばよいというわけではない。
特に0〜2歳は定員が埋まっていることが多く、空いたとしても認可保育園に入っていない保育ニーズのある児童が優先される。
こうした事情も復職を遅らせ、特定の園への入園を待つ動機となる。
距離だけでなく、教育方針や保育所の広さ等で特定の園を希望するケースもある。
こうした条件を絞って保育園を選ぶことは、時に「わがまま」という見方もされる。
しかし、保育園は1日の大半を過ごす場であり、子どもにとって重要な学びの場でもあることを考えると、少しでも子どもに合うところを選びたいと思うのは親として自然なことではないか。
また、類型(3)の地方単独事業は認可保育園に入れなかった人の受け皿となっている。
特色ある教育等により、入園してみたらむしろよかったというケースもあるが、認可保育園が空き次第転園する人も多く、まさに待機児童といえる。
保育料が認可よりも高い場合もあり、コスト面の負担も大きい。