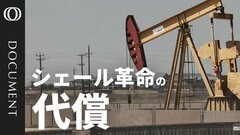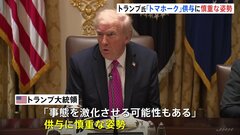(ブルームバーグ):日米同盟の重要性と力強さはかつてない水準だが、不確実性や危機の高まりもこれまでになく深刻だ。東京を最近訪れた際に官民の関係者と世界情勢について語り合った結果、私が得たのはこうした矛盾に満ちた認識だ。
日本周辺では、中国の好戦的なスタンスや北朝鮮による挑発の可能性など脅威が高まっている。しかし、私と会ったほぼ全ての人が最も懸念していたのは米国の現状だ。
日米同盟は第2次世界大戦の激しい敵対関係を乗り越えて築かれた友情の象徴であり、長年にわたり米国のアジア太平洋地域における安全保障の柱となっている。そして今、その重要性は一段と増している。
この地域での紛争リスクが高まり、米国の軍事的優位が揺らぐ中で、米政府は友好国からのより一層の支援を必要としている。世界で最も重要な地域における最強の同盟国である日本の存在は不可欠だ。
さまざまな面で、日米関係は順調に発展してきた。日本は2022-27年に防衛費をほぼ倍増させる計画を打ち出し、防衛力の強化に取り組んでいる。日米両国は、かつて戦略的保護とでも呼ぶべき非対称な同盟関係だったものを、徐々に真の戦闘パートナーシップへと変えつつある。
日本はまた、米国との関係が時に緊張する東南アジア諸国への関与を強めることで、域内での重要性を高めている。インドとオーストラリア、フィリピンとの安全保障協力を強化し、多国間の枠組みに多く参加する日本は、新たに形成されつつある地域安全保障ネットワークの要だ。
しかし、課題もある。27年以降、日本が防衛費を国内総生産(GDP)比2%を超えて増やし続けるのは難しいかもしれない。ヘグセス米国防長官がシンガポールで最近開かれたアジア安全保障会議「シャングリラ対話」で求めたGDP比5%という防衛費水準の達成はさらに困難だろう。
米国が戦略的関心という意味で最優先するのは太平洋地域だと確認したことを日本政府の関係者は歓迎しているが、米軍の新たな中東配備を目の当たりにし、本当に米国のアジアシフトが実現するのかという疑念を拭い切れないでいる。
自由貿易
日米の安全保障協力がかつてなく緊密になる一方で、今後の両国関係を巡り深い不安も存在している。中でも最大の懸念は経済だ。米国のバイデン前政権が安全保障上の理由で阻止した日本製鉄によるUSスチール買収を、トランプ大統領が認めようとしていることは日本で称賛されている。
日本をいら立たせているのは、トランプ氏の関税政策だ。トランプ政権1期目で米国と新たな通商協定を結んだ日本は最も重要な同盟国として、米国に経済的な敵として扱われることはないと見込んでいた。
最悪の関税措置発動を回避するための交渉は合意に向かっているようだ。中国とのリアルな戦争の可能性もある中で、日本には米国との貿易戦争など起こす余裕はない。それでも、米国がこれまで支えてきた開かれた世界経済を自ら放棄しつつあるという危惧は根深い。
石破茂首相と岩屋毅外相は5月下旬のフォーラム「アジアの未来」(日本経済新聞社主催)で、自由貿易を守るために日本と周辺国は協力すべきだと訴えた。その発言の裏には、自由貿易を脅かしているのは米国だという隠れたメッセージがあった。
政治の混迷は日米共通だ。石破政権は少数与党で、次の国政選挙では議席を減らす公算が大きい。そうなれば、不人気な首相に対し与党内からの圧力が高まるだろう。
ただし、誰が首相であろうと、日本で強いリーダーが近く現れる可能性は低く、大胆な経済・安全保障改革を進めるのは難しそうだ。深刻な人口減少問題に真正面から取り組むのは、なおのこと困難だろう。
日本の政治が活力を失っているとすれば、米国の政治は混乱の極みだ。世界の平和と繁栄を支えてきた超大国が、今や同盟国の領土を奪おうとし、気まぐれで無計画な政策で世界経済を翻弄している。
トランプ政権は、米国の経済的優位を支えるイノベーションのエコシステム(生態系)や優秀な外国人人材の流入を攻撃。大統領の危機管理に不可欠な国家安全保障体制を弱体化させている。
根本を突き詰めれば、同盟国や国際的関与に曖昧な姿勢を取り続ける人物が二度にわたり大統領に選ばれたという事実そのものが、長期にわたる「米国第一」の時代の始まりと、米国がかつて主導した国際秩序から離れる兆候ではないかという疑念を抱かせている。
日本にとって、その衝撃は計り知れない。日本は第2次大戦後、米国の庇護(ひご)と支援の下で復興を果たした。米国が後ろに退き、中国が前に出てくれば、地域の均衡は崩れると日本の当局者は認識している。
何十年にわたり、米国との同盟関係は日本外交の基軸だった。この関係が揺らげば、日本が生き残るためには核兵器の保有など、抜本的な政策転換が必要になるかもしれない。もっとも、私が話を聞いた限りでは、日米同盟が破綻するような事態が差し迫っていると考える関係者は誰もいなかった。
トランプ政権下の米国と最も緊密に連携している国の一つが日本だ。しかし、長期的な観点から見ると、トランプ政権が示唆する米外交姿勢の変化にこれほど大きな影響を受ける国は多くない。
今のところ日米同盟は力強く機能している。だが、日本の戦略家らはすでに「ポスト・アメリカ」の世界となる可能性に備え始めている。
(ハル・ブランズ氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。米ジョンズ・ホプキンズ大学高等国際問題研究大学院教授で、シンクタンク「アメリカンエンタープライズ研究所(AEI)」の上級研究員でもあり、「デンジャー・ゾーン 迫る中国との衝突」を共同で執筆しています。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Japan Is More Worried About the US Than About China: Hal Brands
コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:New York Hal Brands hbrands1@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Toby Harshaw tharshaw@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.