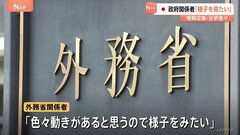ヒト型ロボットは儲かるのか?
ヒト型ロボットのビジネス性について、小倉さんは工場での活用に可能性を見出しています。
「工場で働く人の人件費だと思うと、300万円はめちゃめちゃ安い。特に24時間働けて、しかも5年使えるとしたら、5年分の24時間だから3倍働いているじゃないですか。だから3年間×3で、15年分の人件費が300万だと考えると、めちゃめちゃ安いんですよ」
しかし、本当に人と同じ作業ができるのか、安全性やコストパフォーマンスの問題もあります。また、ヒト型である必然性についても疑問を投げかけています。
「人型ロボットってモーターが大体12個ぐらい足のモーターで使うので、車輪だと2個とかで進むと思うんですけど、そこが本当にいいのかという議論もあります」
Google時代の経験から見えたこと
小倉さんはGoogleが買収したヒューマノイドロボット企業SCHAFTでの経験を振り返り、当時の挑戦と課題について語りました。
「二足で歩くことは絶対に譲らずにやろうと目標があったので、二足で歩くロボットがどういう現場で、どういう仕事ではまるのか、二足である必然性があるかというのを探索したんですが、あまりうまくいいアプリケーションを発見できなかったんです」
Googleでの経験から、「大企業でやってもできないというのは分かったから、小さいところでやってみよう」と思い、起業を決意したと言います。

今後の展望
現在、小倉さんはアイリスオーヤマグループでロボット開発を続けています。
「中国とちゃんとガチンコで量産して戦えるような体制でやっています。サービスロボット、工場じゃないところで働いているロボットの領域で、中国やアメリカじゃない日本の会社としてちゃんと量産して市場を作っていくというのが今のプロジェクトです」
ヒューマノイドロボットについても「ゆくゆくはまたチャンスがあればやりたい」と意欲を見せています。
世界中でヒト型ロボットの開発競争が激化する中、日本の技術力や歴史的な強みを生かせるのか、注目が集まります。
小倉さんのような経験豊富な開発者の挑戦が、日本のロボット産業に新たな風を吹き込むことを期待したいところです。
※この記事はTBS CROSS DIG with Bloombergで配信した「1on1」の内容を抜粋したものです。