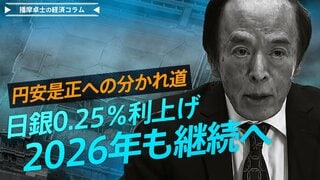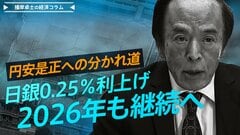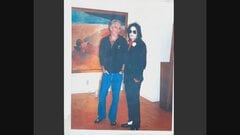上司・部下間の「信頼」の構築が鍵
信頼には「認知的信頼」「感情的信頼」の2つの種類があるとされている(McAllister, 1995)。認知的信頼とは、端的にいうと相手に対して「有能である」「意思決定と行動が一致している等、倫理的高潔さをもっている」と感じているかどうかである。
一方で、感情的信頼とは、相手に対して、「親しみを感じている」「プライベートも含めて相談したいと思う」等、感情的なつながりがあり、弱みも見せられる状態のことをいう。組織の文脈では、直属上司に対するこの2種類の信頼が、上司との間で良質な社会的交換関係を促進し、組織の効率性を高めるだけでなく、従業員のキャリアにも高い生産性と幸福度をもたらすことがわかっている。
この認知的信頼と感情的信頼は、それぞれ異なる性質をもっているものの、お互いが連携し、機能的に補完し合いながら、前述のようなポジティブなアウトカムを出す。たとえば、現部署経験が長く組織内の人から有能であると知覚されている、あるいはカリスマ性のある上司の元では、部下は「この上司についていけば組織は成功できる」と期待し、組織の目標へ向かって一丸となるが、その土台は認知的信頼であり、上司の有能さやカリスマ性だけでは感情的信頼を築くことは難しい。
会議前のアイスブレイク、就業後の何気ない立ち話、お互いの個人的状況の共有など、業務以外の何気ないコミュニケーション等で感情的信頼も築いていく必要がある。
「認知的信頼」だけでも組織は十分機能すると感じる人も多いだろうが、そうではない。実際に、認知的信頼よりも感情的信頼のほうが大事であるという研究結果もある。米国Auburn大学で行われた研究では、上司に対する認知的・感情的信頼が、自発的な職場への貢献や組織へのコミットメントにどう影響するか、210組の上司と部下を調査している。
その結果、上司への感情的信頼は①担当業務への行動(例:担当の業務責任を十分にこなしている)」②担当業務以外の貢献(例:サポートを直接頼まなくても難しい業務を抱えている同僚の手助けを行う)③企業へのコミットメント(例:この企業で自分の残りのキャリアを費やせるなら非常に幸福だ)という3つすべてにおいて効果があった一方で、認知的信頼については関係がないことが明らかにされている(Yang & Mossholder, 2010)。
年下上司・年上部下の関係では、年上部下側が、今までの経験等から自分で判断し、上司には最低限の報告のみのコミュニケーションしか行わず、お互いの信頼関係の構築が難しくなってしまっている等の課題がある。
現在はリモートワークも普及し、効率性を突き詰める組織運営となってきており、「報告・連絡・相談」の時間を簡素化する傾向にもある。しかし、感情的信頼を構築するためには、こういった業務のコミュニケーションのみならず、職場内での雑談に代表される業務とプライベートの間の中間的なコミュニケーションも重要な時間であり、効率化を追求されるなかでも意識して取るべき時間である。
また、上司・部下の相互信頼には「双方向のコミュニケーション」が有意に強く影響し、こうした信頼が、二者関係の安定において肝要とされている(Anderson & Weitz, 1989)。上司側からだけでなく、報告、相談をまめに行う、職場でのコミュニケーションを密にする等、業務連絡も含めた部下側からのコミュニケーションは、年齢や経歴のギャップを乗り越えるためにも、非常に重要な要素である。
日常生活において「感情」は大きな役割を担っているものの、長らく組織行動学においては注目されてこなかった(Robbins, 2009)。しかし、昨今では、心理的安全性、エンゲージメント、組織に対するコミットメントに代表される、従業員の「感情」に対する理解が、組織行動学において重要性を増している。年齢逆転時代においては特に、効率性ばかり追求した組織運営では組織の感情的信頼が侵食され、結果的に組織弱体化を引き起こしかねないことを肝に銘ずるべきである。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員 髙宮咲妃 )