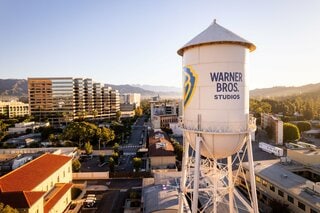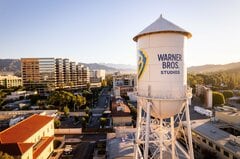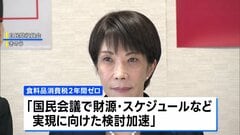・「ドル離れ」の議論はやや注目され過ぎか
・「トリフィンのジレンマ」は今でも正しいとみられるが、金融技術の向上も考慮すべき
・米経済の産業構造は変化しても、経済構造の変化は困難と考えられる
「ドル離れ」の議論はやや注目され過ぎか
トランプ政権の不透明感が意識される中、世界経済の「ドル離れ」がテーマとなっている。米ドルが基軸通貨ではなくなるというやや極端な議論もある。そもそもトランプ政権が始まる前から、米国が占める世界全体のGDPシェアが低下していることなどを背景にドル離れが進むことは自然なことだと言える。しかし、このような動きは非常にゆっくりと進むものであり、市場の不安は行き過ぎたものになる(そのうち自然とテーマではなくなる)可能性が高いと、筆者は予想している。
例えば、ドル離れの議論のきっかけとなった中国の米国債の保有額について、実際のデータを見てみると、確かに減少傾向にある。もっとも、この動きは中国の不動産バブル崩壊というダウンサイド・リスクが意識される動きと連動している。すなわち、人民元相場に下押し圧力がかかり、過度な人民元安を防ぐために政府が人民元買い・ドル売りを進める中で米国債の売却が進んできたと考えるのが自然だろう。したがって、中国政府当局が戦略的に米国債を売却しているとは言い切れない。
確かに、22年2月にロシアがウクライナに侵攻した後、ロシア中銀が保有する米国債(外貨準備)が凍結された際には、中国政府も米国債を売却したいと強く感じただろう。しかし、その後も人民元相場の動きに合わせた程度にしかポジションを圧縮できていないことに鑑みると、急激に米国債を売却することは難しい(中国にとっても不利益となる)ということだろう。中国による米国債の売却(ドル離れ)という議論は、方向性としては正しくても、現実的には難しいナラティブの一種である可能性が高い。