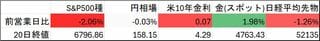USTR(米通商代表部)はインドの輸入要件について、国際基準に適合していないとした上で、品質管理の独自規格の義務化やデータプライバシー制度など非関税障壁の高さを指摘しており、今後の協議においてこれらの問題が交渉材料となる可能性が高い。さらに、上述したようにインドの平均関税率は新興国のなかでも突出しているが、これは伝統的にインドが輸入品に高関税を課すことにより国内産業の保護を優先する産業政策を志向してきたことが影響している。モディ政権もこうした政策を踏襲した上で、『メイク・イン・インディア』のスローガンを掲げ、補助金などにより対内直接投資を促す姿勢をみせた。結果、モディ政権発足(2014 年)以降における対内直接投資は活発化した。

一方、こうした動きにもかかわらず、GDPに占める製造業比率は依然として農林漁業を下回り、その背景に労働者保護の色合いが強い法制度のほか、雇用形態を巡る不透明感が労働集約産業の発展を阻害する一因になっているとされる。さらに、インドの製造業を巡っては、他のアジア新興国に比べて不良品の割合が高いなど生産性の観点で問題を抱える。こうした事情は同国がRCEP(地域的な包括的経済連携)から事実上脱退する一因になったことに鑑みれば、関税率の低さだけを材料に生産拠点が周辺国からインドに移管される動きが促されるかは不透明である。
そして、今後の米国との交渉を通じてインドがどういった条件を飲むことになるかも見通しにくい。各種報道によれば、インド側は米国からの輸入品の半分以上を対象とする関税引き下げを検討しているとされる。しかし、仮に米国からの輸入品に対する関税が大幅に引き下げられれば、米国製品との間で価格競争が激化するとともに、上述したように製造業における生産性が低い状況では生産拠点としての魅力が低下することが懸念される。結果、インドは貿易赤字を背景とする巨額の経常赤字を抱えるなど、対外収支構造はぜい弱であるが、そうした状況は一段と悪化することも考えられる。さらに、米トランプ政権が非関税障壁としてモディ政権が推進してきた補助金政策に焦点を当て、その取り下げや後退を促せば、政策を前提に同国に進出した外国企業による投資活動に影響が出ることも考えられる。また、足元では米国における外国人留学生のうち約3割がインドからの留学生であり、米国にとってインドは巨額のサービス収支上の黒字を生むなか、そのことが交渉材料になるとの見方もある。しかし、トランプ政権による外国人留学生へのビザ取り消しの半分はインド人留学生であるなど、必ずしも交渉を前進させる材料とはなっていない模様である。よって、インドにとっては、トランプ関税という『外圧』をきっかけに製造業の生産性向上やイノベーションの促進に向けた構造変革に繋げられるか、仮にそうした動きを促すことが出来なければ、金融市場が抱く期待は絵に描いた餅に終わる可能性に注意する必要がある。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 西濵徹)