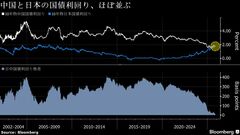(ブルームバーグ):金融庁は18日、楽天証券などのインターネット取引で発生したフィッシング詐欺などによる不正取引が、2月から4月16日までの約3カ月間で計1454件に上ったと発表した。
同庁によると、不正取引は多くの場合、不正行為者が不正アクセスによって被害口座を勝手に操作して口座内の株式を売却し、売却代金で中国株などを買い付けていた。不正な株式の売却総額は同期間で約506億円、買い付け総額は約448億円となった。
金融庁担当者は被害者への補償について、各証券会社が検討中であるとした上で、一般論として今回のケースでは金融商品取引法が原則として禁じる損失補填には当たらず、顧客への損失補償は可能との認識を示した。
また、不正行為者は被害のあった口座で元々保有していた株式を売却して得た資金で、中国株や国内小型株などを買い付けて株価を操作し、別の証券口座からの取引でさやを抜くなどして利益を得ているようだと説明した。
不正取引を巡っては、3月下旬に楽天証で判明して以降、SBI証券やマネックス証券のほか、野村証券、SMBC日興証券、松井証券の計6社で発生したことが分かっていた。同庁の調べにより被害が広がっている事態が明らかになった。
金融庁によると、不正アクセスは1月頃から少しずつ報告があったという。被害は勝手な売買による証券口座内での差額発生などにとどまり、不正行為者により現金が引き出された例はないとしている。同庁はパスワードの使い回しを避け、こまめに口座状況を確認するなど、利用者に改めて注意を喚起した。

証券業界は、不正取引への対策を急いでいる。日本証券業協会の森田敏夫会長は16日の会見で、インターネット取引での不正防止に関するガイドラインを改定する方針を表明。証券各社に、複数の要素を必要とする多要素認証と呼ばれる本人確認の方法を基本的に義務化する方向で議論を進める意向を示した。
楽天証では、不正取引が行われた可能性の高い銘柄について買い注文を一時停止。広報担当者によると、対象は中国株1092銘柄や一部米国株に拡大した。野村証も日本株の一部銘柄でネット経由の買い注文を8日から13日まで停止していた。
(金融庁の説明を追加して更新します)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.