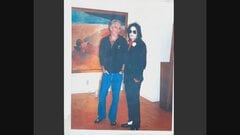なぜ消費に一体感を求めるようになったのか?
また、「トキ消費」の特徴として、「非再現性」に加え、不特定多数の人たちと感動を分かち合う「参加性」、そして、盛り上がりに貢献しているという実感を味わう「貢献性」も挙げられます。
この「参加性」や「貢献性」は、ファンミーティングを例に挙げると分かりやすいでしょう。共通の趣味を持つ他の人々との交流をし、共に感動や楽しさを共有することで参加性が満たされ、また、コミュニティやその場を盛り上げることで貢献性が実感できるのです。
なぜ、このように消費に一体感が求められるようになったのでしょうか。
それは、先に指摘したように、SNSの普及が大きな影響を与えていると言えます。
特に若者は、何をしている最中でも、常に他者と情報や体験を共有しており、このような状況では、個人の消費行動が他者と共有されることが日常的で一般的となっています。
その結果、一体感が自然なものと認識され、「一体感はあって当然のもの、ない方が不自然だ」と考えられるようになったのではないでしょうか。
また、「トキ消費」が進化する中で、情報や体験だけでなく、感想や感動も共有できると認識され、「コト消費」のように個人的な体験として得られる満足感よりも「他者と体験だけでなく、感動も共有できる」満足感が勝ると認識されたことでも、より一体感が求められるようになったと考えられます。
その方法論が今「トキ消費」として確立されているということでしょう。
SNS疲れで「ソロ(おひとりさま)消費」も
一方で、他者との一体感を求める「トキ消費」の存在感が増す中で、現在では「ソロ活」という消費スタイルも一般的なものとなっています。この現象については、どう考えれば良いのでしょうか。
「ソロ活」はもともと「おひとりさま消費」として、消費志向の変化というよりも単身世帯の増加を背景に広まりました。国勢調査によると、2020年で単身世帯は2,115万世帯、総世帯の38.0%を占めています。
単身世帯では、一人で行動する機会が必然的に増えることが多いでしょうが、一人旅やソロキャンプ、一人カラオケなど、積極的に一人の時間を楽しむ行動も支持されています。
その理由は、SNSの普及による「SNS疲れ」が逆効果となって現れたことも影響していると考えられます。
一人で静かな時間を過ごしたり、自分のペースでリラックスできる「ソロ活」がSNSから逃れるための避難場所として機能している側面もあるのでしょう。