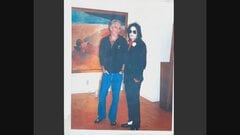「トキ消費」は「モノ消費」「コト消費」に続いて登場
新しい消費スタイルが生まれるたびに「○○消費」という言われ方をされますが、昔から消費の大きな潮流として、所有にお金を使う「モノ消費」、体験にお金を使う「コト消費」があります。
そして、これらに続く形で、2017年に博報堂生活総合研究所が「トキ消費」という新たな概念を提唱しました。
このほかにも、「エシカル消費」「イミ消費」「シェア消費」「ファスト消費」「ソロ(おひとりさま)消費」など、「○○消費」と名のつくスタイルは数多くあります。
一方で、「モノ消費」と「コト消費」は、消費者がそれぞれに費やす支出額のバランスこそ変化しても、今後も消費行動の基盤としてあり続けるでしょう。
また、「コト消費」は「モノ消費」からの価値観のシフトと捉えられ、「トキ消費」はその「コト消費」をさらに発展・深化させたものであるため、他の「○○消費」とは一線を画す存在であると言えます。
新年度が始まり、多くの人が新たな体験に向かう今、あらためてこの「トキ消費」について考えていきたいと思います。
「トキ消費」を求める理由、SNSであらゆる体験に既視感
「トキ消費」とは、博報堂「キーワード解説」によると、「同じ志向を持つ人々と一緒に、その時、その場でしか味わえない盛り上がりを楽しむ消費」ということです。
具体的な例としては、音楽フェスやライブ、聖地巡礼、アイドル総選挙、ワールドカップ観戦、コラボカフェ、ファンミーティング、応援上映、さらにはハロウィンイベントへの参加などが挙げられます。
このほか、少し時間軸を広げて捉えるなら、クラウドファンディングのように「今この瞬間だからこそ支援する」といった行動も含まれるのかもしれません。
「トキ消費」にはいくつかの特徴がありますが、中でも重要なのは「今ここでしか体験できない」「同じ体験は二度と味わえない」という非再現性です。
つまり、体験の限定性に意味を見出すという点で、これは「コト消費」にプレミアム感やライブ性が加わった進化系とも捉えられるでしょう。
このように体験を重視する志向は、バブル期に見られたモノ中心の消費とは大きく異なります。
その背景には、特に若い世代を中心に、モノのスペックよりも心に残る体験や他者と共有できる体験に価値を見出すようになったことが挙げられます。
さらに、スマートフォンやSNSの普及によって、個人の体験が可視化され、いつでも誰かの体験を目にする時代となりました。こうした状況では、あらゆる体験がすぐに共有され、ありふれた体験として既視感を生みやすくなります。
その結果、「自分だけの」「今しかできない」体験への欲求が高まり、再現性が低く、限定性の高い体験を求める「トキ消費」への関心が一層強まっているのではないでしょうか。