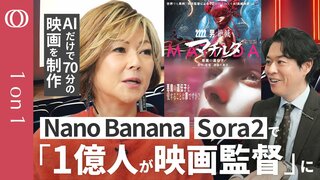企業や宗教団体の少子化対策も出生率改善に効果
企業の少子化対策も、出生率の改善に寄与した可能性がある。
建設会社ブヨングループは、2021年から従業員が子どもを出産した際に、1人あたり1億ウォン(約1100万円)の出産奨励金を支給し、大きな話題となった。男性・女性従業員を問わず、条件なしで支給され、2024年には28人に対し28億ウォンが支給された(2021年から2024年までの累計支給額は98億ウォン)。
また、建設管理およびプロジェクト管理サービスを提供するハンミグローバルは、従業員に第3子が生まれると、入社年数に関係なく職位が一段階昇格する制度を設けた。
さらに、錦湖(クモ)石油化学は、従来の出産祝い金(第一子50万ウォン、第二子100万ウォン、第三子以上100万ウォン)を、2024年から第一子500万ウォン、第二子1000万ウォン、第三子1500万ウォン、第四子以上2000万ウォンに大幅に引き上げた。
企業のみならず、宗教団体も少子化対策に乗り出している。
70万人以上の信徒を擁する世界最大級のメガチャーチである汝矣島純福音教会は、出産祝い金として第一子500万ウォン、第二子1000万ウォン、第三子1500万ウォン、第四子以上2000万ウォンを支給している。
このような企業や宗教団体による破格の出産祝い金の支給は、韓国政府の税制度改定にも影響を与えた。
韓国政府は2024年3月に「企業が職員に支給する出産支援金は、子どもが2歳になるまでは金額にかかわらず全額非課税とする」法案をまとめ、企業側の少子化対策を後押ししている。
今後も出生率は上昇し続けるだろうか?
では、韓国の出生率は今後も上昇し続けるのだろうか。
男性が育児休業を取得し、育児に積極的に関与するなど、意識の変化が少しずつ進んでいることは、希望を持てる要素の一つである。
また今後、第2次ベビーブーム世代(1964年から1973年生まれ)の子どもたちが結婚適齢期を迎えることから、出生率が上昇する可能性も十分に考えられる。
しかしながら、そのためには多くの課題を克服する必要がある。
まず、子育て世帯への支援だけでなく、未婚率や晩婚率の改善に向けた対策を強化する必要がある。出生率の改善には、子育て世帯への支援はもちろんだが、婚姻件数の増加も重要な要素だからである。
また、労働市場のミスマッチを解消し、安定的な雇用を提供するための政策も求められる。そのためには、大学中心の教育システムを見直し、より実践的な職業教育を充実させることが必要だ。
さらに、男女間の賃金格差、出産や育児によるキャリアの中断、ガラスの天井など、結婚を妨げる諸問題を改善することにより、女性が安心して長期的に労働市場に参加できる環境を整えるべきだ。
加えて、ビッグデータを活用し、若者の意識を正確に把握した上で、効果的な少子化対策を講じることが求められる。
これらの課題以外にも、改善すべき点はまだ多く残されている。
今後、韓国は政治的混乱を乗り越え、与党・野党の枠を超えて少子化対策について真剣に議論すべきである。それこそが、出生率を改善するための近道となるかもしれない。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中)