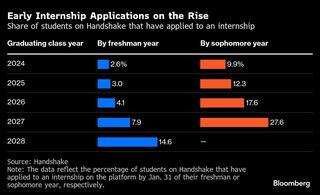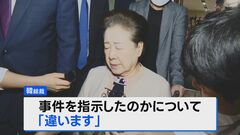(ブルームバーグ):全国の物価の先行指標となる東京都区部消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は、2月に前年比上昇率が4カ月ぶりに縮小し、市場予想も下回った。政府による電気・ガス料金の補助金再開が押し下げ要因となった。
総務省の28日の発表によると、コアCPIは前年比2.2%上昇と市場予想(2.3%上昇)を下回った。日本銀行が目標とする2%を4カ月連続で上回った。電気・ガス代の伸び縮小でエネルギーが6.9%上昇に鈍化した一方で、生鮮食品を除く食料は5.0%上昇と1年ぶりの高い伸び。生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは1.9%上昇と前月から伸びが横ばいとなり、市場予想を下回った。
日銀の1月利上げ以降も、政策委員によるさらなる利上げに前向きな発言や良好な経済指標が続いており、市場には早期の追加利上げ観測も浮上している。今回の消費者物価は市場予想からは下振れたものの、日銀の目標を上回る物価上昇が続く中、市場の追加利上げの時期とペースを探る動きは継続しそうだ。
ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長は、特に際立っている食品価格の上昇を除いた物価の基調は変わっていないとし、「物価上昇の勢いが落ちてきているということではない」と指摘。日銀は緩やかな利上げを継続していこうとしており、「今回の結果はそれを妨げる内容ではない」と語った。

赤沢亮正経済再生担当相は同日の閣議後会見で、電気・ガス料金負担軽減支援事業によるエネルギーの上昇幅縮小などがCPIの伸び縮小の要因と説明。1-3月使用分が対象の同事業の今後の取り扱いについては、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済が実現するまでの間「痛みが生じている家計や企業」に必要な対策を講じる方針を示した上で、物価や賃上げの状況を今後も注視すると述べるにとどめた。
予想を下回るCPIの発表後、東京外国為替市場の円相場は一時1ドル=150円15銭まで下落した。その後はトランプ米政権の関税政策を懸念した日本株の大幅下落を受けて、149円台前半に上昇している。
コアCPIを上回る伸びが続いている総合指数は2.9%上昇と伸びが縮小し、市場予想を下回った。植田和男総裁は12日の国会答弁で、生鮮食品を含む食料品の値上がりは必ずしも一時的ではないとし、消費者心理やインフレ期待に影響するリスクも考慮して政策運営を行う考えを示した。
賃上げの価格転嫁動向をみる上で注目されるサービス価格は0.6%上昇となり、伸びは前月から横ばいだった。
大和証券の末広徹チーフエコノミストは、コアCPI低下の主因は電気・ガス代の補助金の影響で、「生鮮食品を除く食料は引き続き押し上げに効いている」と指摘。その上で、日銀の政策運営について「米など食料の上昇を重視して利上げをするのか、それともサービスを中心に第2の力があまり強くなっていないので様子を見るのかという判断だ」と述べた。
総務省の説明:
- 総合・コアの前年比プラス幅縮小に最も寄与したのはエネルギーで、押し下げ寄与はマイナス0.32ポイント
- 生鮮食品を除く食料は米類や鶏卵などがプラス寄与。米類は前年比77.5%上昇で過去最大の上昇率を更新
- コア前年比の上昇品目数は522品目中354品目で前月の367品目から減少。下落品目数は103品目で前月の95品目から増加
- サービス価格で通信・教養娯楽関連サービスのマイナス寄与は、外国パック旅行の特殊要因や宿泊料が影響
(赤沢経済再生相のコメントや総務省の説明を追加して更新しました)
--取材協力:野原良明、氏兼敬子、照喜納明美.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.