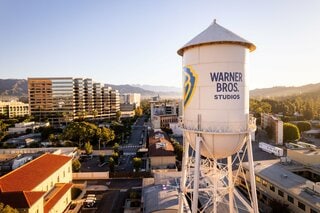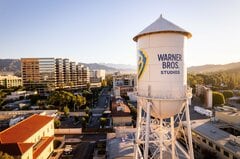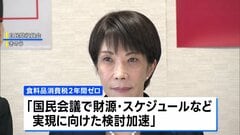●日銀はインフレの背景に「人手不足感」を追記したが、利上げは受け入れられない公算
●マクロ統計ではボトルネックは確認できない
●バッファーがなくなっていることが、人手不足感の高まりの背景か
●家計の高い黒字率が続いている間は、需給ギャップの引き締まりを背景とした利上げは困難
日銀はインフレの背景に「人手不足感」を追記したが、利上げは受け入れられない公算
1月24日に日銀が公表した展望レポートでは、「消費者物価の基調的な上昇率は、人手不足感が高まるもと、マクロ的な需給ギャップの改善に加え、賃金と物価の好循環が引き続き強まり中長期的な予想物価上昇率が上昇していく」とされた。24年10月展望レポートから「人手不足感が高まるもと」という文言が追加され、今後は利上げの根拠として人手不足を前面に押し出していく可能性が高まった。
もっとも、2つの理由から人手不足を根拠に利上げを実施していくことは困難を伴うと、筆者はみている。1つ目は、利上げによって需要を弱めるという考え方が受け入れられる可能性は低い点である。植田総裁は「潜在成長率の推計値を若干下げた理由は、人手不足であります」(1月24日の決定会合後の記者会見)と説明した。供給力が想定より弱かったのでインフレ率をコントロールするために利上げによって需要を弱めるという考え方は、教科書的には正しいロジックである。しかし、日本経済は停滞している(需要は強くない)という見方が一般的であることを考慮すると、利上げによって需要を弱めるという主張は世論に受け入れられないだろう。おそらく、需要を弱めることでインフレ率を安定させるのではなく、供給力を強化することでバランスすべきだという拡大志向の方が政治的にも受け入れられやすい。その結果、出来るだけ金利を低くして供給力強化のための設備投資を促すべきだという高圧経済的な主張が日銀の利上げを阻むことになるだろう。
2つ目の理由は、人手不足感が高まることの問題点として考えられるのが、賃金インフレの発生であることである。むろん、粘着性のある賃金インフレが制御不能なほど強くなる場合、望ましくないインフレ高進につながる可能性はある。しかし、日本経済では依然として高い賃上げ率が望まれている状況にある。なぜ利上げによって賃金インフレの高まりに対して水を差すのだろうか?、と考える人がほとんどだろう。
おそらく日銀は、家計が節約志向というデフレ的な行動を変えずに個人消費が盛り上がりを欠いた状態が続いている(需給ギャップが引き締まらない)という現実を受け入れ、人手不足問題に利上げの根拠を求め始めたようだが、以上の理由によって利上げの推進は困難を極めるだろう。
なお、人口減少社会の下では、供給力も需要も弱まることは自然なことである。潜在成長率が低下しているという分析自体は、筆者も同感である。また、過度に硬直化した金融政策は通貨(円相場)の安定を阻害するという考え方から、現在のようなインフレ局面において機動的に利上げを実施することにも賛成である。しかし、人手不足だから利上げを実施するという説明には無理があると、筆者は考えている。