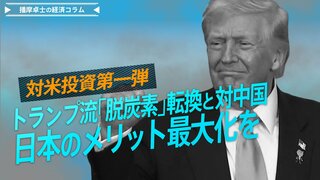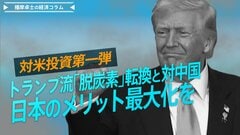強まる累進性強化への反発 “低所得者になる”ための情報も
税制においても社会保障制度においても、「能力に応じた負担構造」は累進性を高める制度改革の旗印となっている。ただ、負担能力のある人≒中高所得者であり、その多くは現役の勤労世代だ。「能力に応じた負担」を追求することと制度の「働いたら負け」の性格を強めることとは表裏一体の関係にある。
こうした中で“低所得者になる”ための情報も溢れている。マイクロ法人の設立、年金の繰り上げ受給(年金を早めに受け取り毎年の給付額を減らす)などがそれに当たるだろう。累進性強化が進むほどに、こうした財テク情報の価値は上がっていく構造にある。リチャード・クー氏の著書「『追われる国』の経済学」(2019年)には以下の一節がある。“これまでリスクを取って人一倍働いて、事業に成功した実績のある人々の多くが、今では相続税の負担をどう軽減するかに多大な時間を費やしている”、“彼らのような有能な人材は、本来なら事業の拡大や新たな夢の実現に全エネルギーを投入してほしいのに、その彼らの多くがこうした後ろ向きの話題で頭が一杯なのである”。
累進性強化は長年、財政健全化、社会保障制度維持の文脈で淡々と進められてきた。しかし、世論の声を反映して実現した児童手当の所得制限撤廃、現役世代の所得税減税を訴える国民民主党の躍進などにはこうした流れの揺り戻し、潮目の変化もみられる。今年7月には参院選も控えている。経済政策の大きな方向性を考えるうえでも重要な意味を持つだろう。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 星野 卓也)