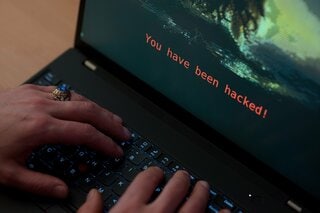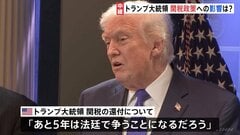流行当時と意味合いが異なる“働いたら負け”
「働いたら負け」という言葉が2004年に流行した。若年無業者を指す「ニート」とともに広まった言葉である。底流にあったのは、雇用環境の悪化に伴う“諦め”のようなものだったと考えられる。当時は就職氷河期だ。
昨今は違ったニュアンスでこのフレーズを見かけることが増えてきたように思う。税や社会保障制度の改正における「低所得者を優遇し、中・高所得者の負担を拡大する政策」に異を唱える文脈だ。これらの政策に対する風当たりが明確に強まっているように思われる。
2000年代ごろから税制度においても社会保障制度においても、累進性の強化が進められてきた。所得税においては、最高税率の引き上げのほか、基礎控除や配偶者控除に対する所得制限、給与所得控除の上限引き下げなどが進められたほか、相続税でも基礎控除引き下げや最高税率の引き上げが行われた。
社会保障制度では給付段階において低所得者を優遇、高所得者に負担を求める措置が数多く設けられている。例えば、健康保険における高額療養費制度は、医療費の自己負担額が限度額を超えた際に超過分を補填する仕組みだ。その限度額は所得階級によって異なる。2015年に現役世代の所得区分を3から5段階とし、高所得者の限度額を引き上げる改正が行われた。今般、この所得区分を13段階にする改正が27年にかけて進められる見通しとなっている。最も所得の高い層の月当たりの負担上限額は25万円強から44万円強へと7割以上の引き上げとなる。
また、健保加入の雇用者の場合、所得区分の基準として主に用いられるのは社会保険料の算定に用いられる標準報酬―つまり働いて得る賃金収入である。ほかに不動産収入、金融収入が多くあっても、なぜか「働いて得る収入」が判定基準になる。これは同じく厚労省の制度である在職老齢年金でも同様であり、“賃金収入”と年金収入が一定値を超えた場合に年金を減額する。厚労省の制度が管轄している所得の数字が社会保険料算定の際に用いる標準報酬であることに根があるのだが、働いて得た所得だけが判定基準として用いられる点は一層 “働いたら負け”の性質を強めている要素でもある。