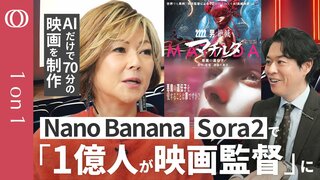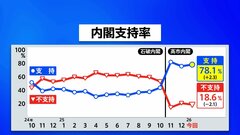日本の無痛分娩の利用促進に関する課題
【無痛分娩にかかる費用負担】
日本において無痛分娩が普及しない課題の一つ目として、費用負担があげられる。一般的に無痛分娩の費用は、出産費用に加えて10万円~20万円ほどが必要と言われており、健康保険の対象ではないため全額自己負担となる。ちなみに、出産費用(正常分娩)の全国平均(令和6年度上半期平均値)は、51万7,952円と毎年増加しており、これに個室代や食費などを含めた合計は58万円9794円と報告されている。これに対し現行の制度では、出産育児一時金の50万円が支給されるため、直接支払い制度を利用すると相殺できそうに思われるが、実際には東京都など都市部を中心に45%で出産費用が出産育児一時金を上回っている。東京都を例にあげると、出産費用の平均が62万円で出産育児一時金を差し引いた12万円が自己負担額、これに無痛分娩費用が加わると22万円~32万円ほどかかる計算になる。実際には、麻酔の追加有無や分娩後の管理内容、入院期間等の影響で、最終的な金額が100万円以上となる例も散見される。直接支払制度を利用していない方だと、一旦全額自己負担した上で、一時金の請求をすることになるため、家計から多額の持出しが必要となる。さらに、産後の身体に必要な産褥帯やナプキン代、子どもを迎えるための育児物品の購入費用や環境整備代、人工乳やおむつなどの育児消耗品等が必要であり、出産費用だけ用意すれば良いわけではない。2022年に実施されたある調査では、無痛分娩の最大のハードルとして費用面があげられており、余裕がある家庭しか選択できない分娩方法であると指摘されている。
冒頭で紹介したように、今後の無痛分娩に関する公的な費用助成の実現可能性は不明ではあるが、2024年現在、正常分娩の保険適用について議論が進んでいる。少なくとも出産費用に関する費用負担が軽減されると、無痛分娩も選択されやすくなる可能性が高い。費用面の課題をクリアして、子どもを希望する方々が安心して出産に臨める社会の実現が望まれる。
【分娩施設の分散と産科麻酔科医の不足】
次に、日本における分娩施設の分散と産科麻酔科医の不足について指摘したい。日本では、分娩を取り扱う産科医療機関や助産所が分散しており、ひとつの医療機関あたりの取り扱い分娩数が少ないのが特徴的である。ある調査によると、1,000件以上の分娩を取り扱う施設が112施設ある一方で、200件未満しか取扱いがない施設が全国で676施設もあることが指摘されており、その中には年間数件程度の分娩を産科医ひとりが対応している例も存在している。無痛分娩が一般的である欧州では、産科医療機関が日本ほど分散しておらず、産科医も産科麻酔科医も集約されているため、無痛分娩を含め24時間態勢で受け入れることが可能である。分娩アクセスが容易であることは重要であるが、全てのお産が医療介入不要な正常分娩とは限らないため、少子化が進み分娩件数の減少と高齢出産による周産期リスクの増大が見込まれる日本では、分娩施設と人材の集約化を検討すべきではないだろうか。
また、産科医とは別に、緊急帝王切開や無痛分娩における麻酔を担う麻酔科医を確保できないことも無痛分娩が普及しない大きな要因となる。厚生労働省によると、2022年時点における医師数は、34万3,275人で過去最多となっているが、産科および産婦人科に従事する医師数は、1万1,833人と全体の3.7%ほどになる。また、麻酔科に従事する医師数は、1万350人と全体の3.2%ほどになるが、日本産科麻酔科学会の登録数は、麻酔科医が691人、産婦人科医が674人と報告されており、安全で質の高い無痛分娩を普及するためには、人員体制のさらなる強化が求められる。無痛分娩は分娩進行と麻酔管理を同時に実施する必要があり、産科医がひとりで担うには負担が高すぎる。現状、無痛分娩が可能な施設でも、産科麻酔科医が不在となる勤務(時間)帯には無痛分娩に対応しないと明記しているところもあり、専門医の不足が無痛分娩の提供体制に影響を与えていることが分かる。産科麻酔科を大幅に増員し、無痛分娩の普及率を諸外国の水準にまで引き上げることは容易ではないが、麻酔科専攻にインセンティブを与えるような動きや、自治体独自の出産費用補助制度も見られるようになっている。2025年1月6日には、東京都が都内在住の妊婦を対象に無痛分娩の費用助成を実施する方針であることも報道された。今後も、日本で安心して出産に臨めるよう無痛分娩の提供体制に関する議論が活発化することが期待される。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛)