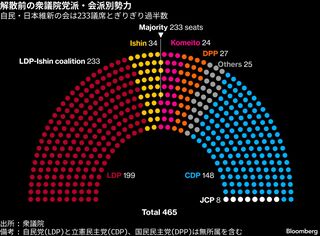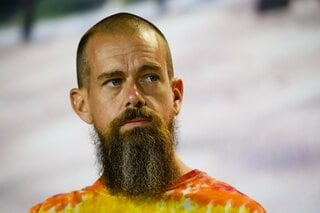着実に進む株主・投資家向けのサステナ情報開示。消費者への浸透・理解は大きな課題
本稿では、2024年8月に実施した調査に基づき、サステナビリティに関するキーワードの消費者の認知・理解について分析した。サステナブルな社会の実現に向けては、政府・行政機関、株主、投資家、金融機関、企業、事業者団体、NPO・NGO、消費者などの多様なステークホルダーが関与している。
冒頭の国連のSDGsレポート(The Sustainable Development Goals Report)では、2030年のアジェンダ目標達成に対する危機感が示されている。
株主や投資家に対しては、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)等による情報開示基準の制定が進められており、サステナビリティに関連した企業の価値創造の透明性向上に向けた取り組みが着実に進んでいる。
しかし一方で、「循環型経済モデル」や「責任ある消費(Responsible Consumption)」のさらなる促進に向けて、市民や消費者による広範で積極的な支持と自発的な取り組みが欠かせない。
今回の調査から、2023年の調査と比較して「3R/4R」、「SDGs」、「ウェルビーイング」、「グリーン・トランスフォーメーション(GX)」など、サステナビリティの中核をなすキーワードの認知率・理解率は着実に増加していることがわかった。
しかし、全般的には2023年に比べて低下したキーワードが多く、伸び悩みの傾向を示している。
特に、消費の観点からは「エシカル消費(倫理的消費)」は依然として認知・理解ともに十分に高いとは言えない。
「伊藤レポート 3.0」(SX 版伊藤レポート)では、企業が社会の持続可能性に資する価値を消費者に提供し、企業の長期的な成長原資を稼ぐ力を高めていくことで、社会のサステナビリティと企業のそれを「同期」させることが重要とされている。
そのためには、2030年に向けて、「責任ある消費」や「循環型経済モデル」の主な担い手である、消費者のサステナビリティの認知と理解、そして行動を後押ししていく必要があり、さらなる社会的な啓発や、新たな取り組みが求められていると思われる。
本稿では、一定の世帯金融資産や年収水準があり、かつ、世帯年収が高まる、または年代が60代を超える場合、キーワードの認知と理解が進む傾向が確認された。
サステナビリティ・マーケティングの観点では、高世帯年収層と資産形成層では、サステナビリティに関する認知・理解の特徴に違いが見られ、それぞれ異なる側面からサステナビリティへの態度が形成されているとも推測される。
れらの層が「循環型経済モデル」や「責任ある消費」を推進する社会的役割を担っていくことへの期待を込め、引き続き注目していきたい。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員 小口 裕)