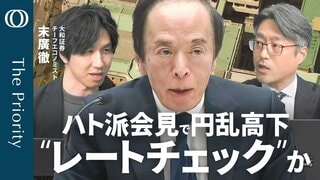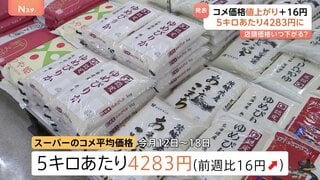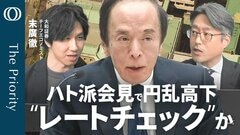なぜ、クレジットカードが伸びたか?
首位のクレジットカード業は、この約9年間に1.9倍も伸びている。まさしく高成長の業種である。ところで、なぜ、クレジットカード業がこれほど大きく伸びたのか。大手クレジット会社には、銀行系、流通系、ネット系などがあり、いずれにも属さない独立ブランドもある。
伸びている市場は販売信用である。高成長の理由には、EC取引の拡大があろう。インターネット通販などのサイト決済では現金を使うことはない。だから、そうしたEC取引が増えれば、自ずとクレジットカード利用も増える。経済産業省のサイトでEC取引金額の推移を調べると、2015年から2023年までに13.8兆円から24.8兆円へと1.8倍に規模が膨らんでいる。拡大するネット取引の決済手段として、クレジットカード業も成長したということだ。
次に、2位の公営ギャンブル=競馬、競輪、競艇、オートレースは意外な結果だろう。実は、この4つのうち、最も伸びているのは競艇(2.5倍)だ。そして競輪(2.1倍)、オートレース(1.8倍)である。競馬は4つのうち最も低い(1.5倍)。おそらく、同じ競馬でも地方競馬は、上昇率ではより大きく伸びていると思われる。理由は、ネット取引(ネット投票)という賭け事の手段が、コロナ禍で普及したことが大きいと思われる。遠隔地の参加者を、ネット取引は大きく取り込んだ。最近、筆者が飲食店で相席した隣の男性の手元には競馬新聞があって、熱心に紙面を凝視していた。遠くの地方競馬の欄に赤鉛筆で丸が付けられていて、研究の跡があった。筆者は賭け事の知識が乏しいが、この人はネット投票で遠隔地の競馬を楽しんでいるのだと直感した。ネット取引で賭け事ができると、都市部ではなく地方にあるレースにも関心が及ぶ。こうした賭け事の人気は、まさしくDXの好事例だと思える。また、ギャンブルは、政府が住民税非課税世帯向けに、給付金支給を最近頻繁に行っていることも、一因になっているようだ。この話は、困窮者支援事業に関係している人からも聞いた。
3 位のインターネット広告、4位のソフトウェア開発も、ネット産業の隆盛を反映する。5位の証券は、ネット株式取引もあるが、暗号資産取引やFX取引の市場拡大によって事業が大きくなっていることを反映しているのであろう。やはり、金融取引のネット化の影響である。
少し順位は下がって、10位の宅配業も、EC取引が普及したことで、自宅に届ける宅配ニーズが飛躍的に伸びたのだろう。ネット取引そのものではなくても、周辺分野でそれに連動するかたちで取引量が増えているのだ。クレジットカード=販売信用や、宅配の利用拡大は、ネット取引の派生需要が膨らんだためだと説明できる。昔から、「ゴールドラッシュで儲けたのは、金を掘った人ではなく、ツルハシを売った人だった」と言われる。
高齢化の派生需要
日本の成長産業のベスト10のうち、7つまでがIT関連またはデジタル化の派生によって成長した産業であった。そうした意味で、DX関連が日本の高成長分野だという表現は間違いではない。次に、そうしたデジタル関連以外の成長分野に注目してみたい。以下に挙げるのは、ベスト15のうち、デジタル関連以外のランキングである。
7 位 医薬品・化粧品等卸売
8 位 ペットクリニック
9 位 自動車レンタル・個人向け
11 位 ホテル
12 位 廃棄物処理
13 位 その他の洗濯・理容・美容・浴場
14 位 貸金業
15 位 医薬品・化粧品小売
このランキングからは、人口高齢化という流れが見えてくる。7位の医薬品・化粧品等卸売は、医療需要がコロナ禍で高まったことや、高齢者医療の需要拡大がある。化粧品の世界では、アンチエイジング市場の成長もある。美肌、細胞活性化などの謳い文句は、年齢層の高い消費者向けであろう。ほかにも、13位のその他の洗濯・理容・美容・浴場にも、美容ビジネスが含まれている。15位の医薬品・化粧品小売も同じくアンチエイジング市場の成長がある。
8 位のペットクリニックも、微妙に高齢化が絡んでいる。ペットの犬と猫の数では、猫が逆転して増えたことが、数年前にニュースになった。飼い主が高齢化していることも影響しよう。子供が独立した家庭では、犬や猫を飼い始めるケースは少なくない。その犬や猫も高齢化していて、クリニックのお世話になる機会も増えている。