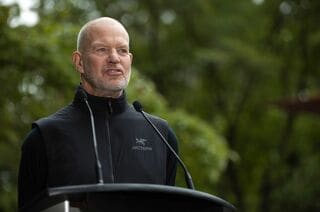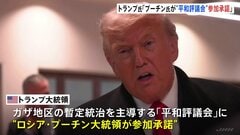(ブルームバーグ):自民党と日本維新の会が20日に交わした連立政権合意書には、来年の通常国会を期限とする「対日外国投資委員会(日本版CFIUS)」の創設が盛り込まれた。耳慣れない言葉だが、実際に設立されれば海外からの対日投資に影響を及ぼす可能性もあるCFIUS(シフィウス)を解説する。
本家は米国
米国の対米外国投資委員会(CFIUS)は、国家安全保障の観点から外国から米国への投資を審査する省庁横断の組織だ。技術や機密の流出、基地近くの土地取得によるスパイ活動などを防ぐために投資の是非を審査している。米財務省、国防総省、国務省などの合議制で、最終決定を大統領が行うこともある。
外国企業が企業買収や不動産取得に当たってCFIUSの事前審査に出すかどうかは任意だが、財務省内に疑わしい取引を調査する専任チームを持ち、小さな取引であってもさかのぼって取り消される可能性がある。実際に未届けで完了していた出資が、3年以上たってから売却を命じられた例も珍しくない。
日鉄、ブロードコム
CFIUSの審査が大きな注目を集めた例としては、2023年に日本製鉄が発表したUSスチールの買収計画がある。米大統領選を控え、米国を象徴する企業の一つを海外企業の手に渡すかどうかが政治問題化した。18年のブロードコムによる米クアルコムに対する1170億ドル(当時のレートで約12兆4200億円)規模の敵対的買収計画も中国の脅威などを理由に撤退に追い込まれた。
どういった取引が対象になるかの基準は非公開だが、外国政府や政府系企業の関与や、国家の安全保障に関連した重要技術、インフラ、個人データ関連企業、注目度の大きな企業の経営権の取得などが勧告を受ける可能性がある。技術関連などの指定業種であれば、少額出資でも審査対象になることがある。
新閣僚が創設に意欲
日本版CFIUS構想の全容はまだ見えないが、早速創設への意欲を口にする閣僚もいる。片山さつき財務相は21日、記者団に対し、創設は「非常に適切」とした上で、日本の国益や安全保障の観点で日本企業をどう守るべきなのかについては「大きな問題なので、ぜひきちっとして参りたい」と述べた。

高市早苗首相は9月の自民党総裁選出馬会見の中で、自身の政策として「海外からの投資を厳格に審査する対日外国投資委員会を設置する」と言及している。維新も9月に公表した政策提言で、外国人や外国資本による土地取得を規制する目的で同委員会の創設を訴えていた。
これまでは手薄
CFIUS創設について、欧州系コンサルティング会社ローランド・ベルガーの日本法人シニアパートナー、田村誠一氏は「これまで、米国のCFIUSのような国家安全保障の観点から外国資本による企業買収や投資を監視する仕組みが日本は極めて手薄だった」と指摘する。現在日本は外国為替及び外国貿易法(外為法)で外国からの投資を審査しているが、「拒否された取引は非常に少なく、人員不足で実効性のある審査ができていないというのが実態だった」とし、新組織の審査能力の向上に期待を寄せる。
田村氏はまた、地政学リスクが高まっており、米国のような省庁横断的な常設の委員会を作ることで、関心事が異なる各省庁が「多面的な視点できちんと審査する意味は大きい」とし、不動産の取得規制もこの仕組みに一本化する方がよいとの考えを示した。
政府規制の影響
規制の強化が、日本市場の健全性を損なう懸念があるとの意見もある。オーストラリア国立大学のシロ・アームストロング教授は24年12月のリポートで、経済安全保障を追求するために政府による介入が拡大すれば、「日本の開放性、競争力、生産性に対して新たなリスクをもたらす可能性もある」と指摘した。
対日投資に冷や水を浴びせる可能性はあるのか。日本株に投資する米サファイアテラ・キャピタル最高投資責任者(CIO)の細水政和氏は「特に懸念を感じていない」と話す。日本版CFIUSは本家の米国版と同様に、外資規制の形式をとりつつも実質的には対中国資本規制になると想定されるためだとした。
日本貿易振興機構はリポートで、これまで米CFIUSによる勧告に基づいて大統領が買収禁止を決定した案件は全部で9件あるとされており、日鉄の件以外は全て中国が何らかの形で関与していたと指摘している。
むしろ成長の機会に
ローランド・ベルガー日本法人のシニアパートナー、中川勝彦氏は「CFIUSの創設を経済成長につなげる機会としてほしい」と期待を示す。日本は国がどの産業を重視しているのか見えにくく、安全保障の観点から守るべき産業を明確に示すことは「成長の後押しになる」と指摘した。
--取材協力:清原真里.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.