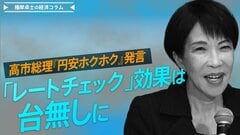注目すべきはむしろ受給資格期間の延長
今般の決定で注目すべき点は、受給資格期間の延長が盛り込まれたことである。実は、これまでの議論の中でほとんど触れられてこなかった。内容としては2030年以降、受給資格期間を現行の15年間から20年間に段階的に延長していくというものである(強制)。具体的には2030年以降2039年まで1年毎に半年(0.5年)引き上げられることになる。これは年金財政の安定化を考えた上での措置と思われる。
中国では年金保険料を受給資格期間である15年間納付した後は納付をやめてしまうといった状況が発生している。その点を考慮すると、2030年までは定年延長を選択すると、年金保険料の納付期間が延びてしまうので、それを回避するために定年延長の選択がそれほど進まない可能性がある。加えて、2030年以降に受給資格期間が延びても、中国の場合は定年退職時に年金保険料の一括追納も可能である。そのため、不足分の年金保険料が一括納付できる範囲であれば本人が定年を延長する必要はない。
その一方で不足分の年金保険料を一括納付できない場合には、保険料納付のための定年延長の選択も考えられる。定年延長のための引き上げペースは1年で0.2歳(年)または0.33歳(年)であるが、受給資格期間の延長は1年で0.5年である点を考慮すると、定年延長と一括納付の増額を組み合わせなければ受給資格を得られなくなる。穿った見方かもしれないが、政府は定年延長のみでは、実際それほど進まない点を考慮し、受給資格期間の延長を盛り込んだ可能性もある。
就業率は3割以下という現状
定年延長が適用されるのは都市で働く会社員が中心となるが、2020年の国勢調査に基づいて都市部の男性の就業率を算出してみると50-54歳時点で80.8%、定年目前の55-59歳では66.5%まで低下している(図表1)。今般発表された延長後の定年退職年齢(63歳)を含む60-64歳については2020年時点で27.1%と3割に届かない状況だ。一方、女性については男性よりも定年退職年齢が早いこともあり、50-54歳時点では44.5%、延長後の定年退職年齢(55歳、58歳)を含む55-59歳については24.8%とこちらも3割には満たない。更に、男女とも定年退職年齢以降の就業率は下がる一方だ。定年延長による労働期間の延長(労働人口の増加)もあるが、中国の場合は高齢者の労働市場も同時に整備していく必要がある。

定年延長については雇用主である企業と協議の上決定することになっており、企業の人事体制、社会保障・人件費のコスト負担など経営に大きな影響を与える。これまで法定退職年齢に達すると労働契約が終了していた点を考えると、今後は定年延長の社員に対する作業環境や職場の整備、職務の再設計、柔軟な働き方や賃金設定の検討など更なるコストや準備の増大も考えられる。中国において現時点では上掲の負担をすべて企業側が背負うこととなる。政府が定年延長を積極的に進めたいのであれば、その主体となる企業への助成も必要となってくるであろう。日本の場合は、例えば65歳以上への定年延長や高年齢者向けの雇用管理制度の整備などを目的とした65歳超雇用推進助成金が設けられ、受け皿となる企業へのサポートがはかられている。今後は企業による受け入れ促進を目的としたサポート措置の整備も必要となってくるであろう。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員 片山ゆき)