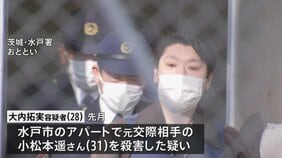加害者への複雑な感情
今年1月、最高裁は弁護団の特別抗告を棄却する決定をしました。しかし、まだ刑は執行されていません。貴子さんの父親は一貫して死刑を求めていましたが、その思いを抱えたまま亡くなりました。貴子さんは複雑な心境を語ります。
貴子さん
「判決が決まったからには、それを執行してほしい。そうあるべきじゃないかなとは思いますけど、母親を殺されたんだから、犯人は死んでくれればいいって思うかというと、そういう感情とはなんかちょっと違う感じがします」
一方で、父親の思いを叶えてあげられなかったという悔しさも抱えています。
貴子さん
「父の思いを晴らしてあげられなかったという意味においては、父に申し訳なかったという思いはあります」
被害者支援の空白期間
この事件が起きた2013年、被害者や遺族を支援する体制はまだ十分に整っていませんでした。貴子さんは弁護士を自分で探し、被害者支援センターなどの支援を十分には受けられませんでした。被害者や遺族が刑事裁判に参加し、意見を述べることができる「被害者参加制度」や特別休暇の取得についても、情報が十分に提供されていませんでした。

1審の裁判に向けた打ち合わせで訪れた弁護士事務所で、初めて支援者と出会った貴子さん。支援者から、被害者参加制度や特別休暇の制度を知らされたのは、裁判が始まる1週間前でした。「何ができるかを知らなかったので、自分でどうしないといけないかを考えることもなかった」と貴子さんは振り返ります。
教育現場への問いかけ
佳代さんは現在、被害者支援や犯罪被害について学校で教えることの重要性を感じています。
佳代さん
「自分が被害者になった、当事者になった後で考えると、自分で支援をしてもらえる場所に出向いて話を聞いたり、支援を受けたりということができるかもしれないけど、自分が当事者になる前ってそういう当事者意識が全くない。学校でそういった知識みたいなものを広めるような機会がもう少し多くあってもいいんじゃないかなと思います」
教育を通じて、いじめなどさまざまな問題の改善につながる可能性があると考えています。