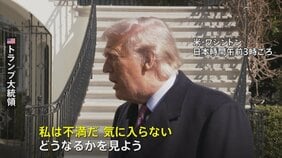代表的なひっつき虫の種類
早坂徹園長に園内を案内してもらうと、園内でも何種類ものひっつき虫と呼ばれる植物を見つけることができました。

仙台市野草園 早坂徹 園長
「ひっつき虫と一言で言っても多くの種類があって、これから秋が深まってくると見られる種類はもっと増える」
見せてもらったのは、トゲだらけの楕円形の果実を持つイガオナモミ。表面に細かい毛が付いていてペタリとくっつくフジカンゾウ。葉に小さなギザギザがついたミズタマソウなど。



ほかにも、ひっつき虫の主な種類を紹介します。皆さんのイメージしたものはあるでしょうか。

アメリカセンダングサ:雑草として道端や空き地など私たちの身近にも非常に多く生息している。アメリカからの帰化植物。いがぐりのように放射状に集まった果実ひとつひとつが扁平なくさび形をしていて、先端に鋭いトゲがありひっつく。

イガオナモミ:クリの“いが”に似たトゲだらけの果実が特徴で、ひっつき虫の代表格の一つ。

オオオナモミ:イガオナモミよりもやや長い楕円形。イガオナモミ同様アメリカからの帰化植物で、在来種の「オナモミ」はオオオナモミやイガオナモミの繁殖力におされて今では絶滅危惧種になっている。私たちが普段オナモミと呼んでいるものはほとんどがオオオナモミやイガオナモミ。

コメナモミ:果実を包み込むようになった部分の表面に毛が密生しており、そこからネバネバした粘液を分泌してひっつく。

チヂミザサ:葉の縁が波打つように縮れているのが名前の由来。繁殖力が旺盛で日陰でも良く育ち、ネバネバした粘液を出してひっつく。

ヌスビトハギ:果実のさやが泥棒(盗人)が抜き足差し足で歩く時の足跡に似ていることから名付けられる。 果実の表面に先端がカギ状に曲がった細かい毛が密生 していてひっつく。
このように、植物によってひっつく方法も様々です。早坂園長によると、大きく分けて「トゲが刺さる・ひっかかる系」と「ネバネバした粘液でくっつく系」があるそうです。