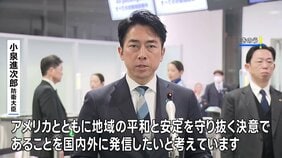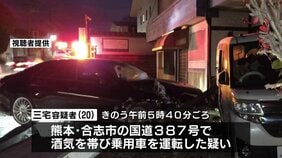半世紀に及ぶ「減反政策」
「おコメが足りない!」と各地で言われていますが…そもそも日本は半世紀もの間、作付けを減らしてきた歴史があります。それが「減反政策」=田んぼを減らす政策です。穂が実る前の稲を刈り取るいわゆる「青刈り」。減反政策は、米余りを背景に1970年から2017年まで続きました。

田んぼを大豆や麦畑などに変える転作を奨励、協力する農家には補助金が支給されました。自由競争を促すことを目的に減反政策は廃止されましたが、その後も自治体やJAなどでつくる協議会が「生産の目安」を示すなどし事実上の生産調整が続いているのです。
宮城県内の主食用米の作付面積を見てみると、2024年は5万8400ヘクタールで前の年より1200ヘクタール増えています。ただ、注目してほしいのが「過去10年分」です。10年以上前と比べると、県内での作付面積は1万2000ヘクタールも減少。収穫量も4万7500トン減っています。

コメの量を減らしてきたので、需要が一気に増えて価格が上がるのは当然の結果かでは?宮城大学の大泉名誉教授も「これまでの需給管理は非常にタイトで、綱渡りだった。何かがあるとすぐコメ不足に陥る可能性があった」と減反や生産調整の課題を指摘しています。これに対し、農水省の出先機関である東北農政局は「現在は、生産者や産地が自らの経営判断で生産に取り組んでいます」と他人事のような回答でした。