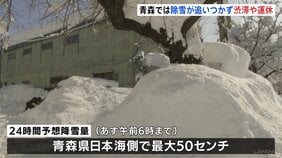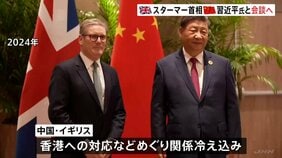▼国内に4万人以上 施設で暮らす子どもたち
広島修道院には、事情があって親元を離れている100人あまりの子どもたちが、共同で生活をしています。かずまくんは、学年の違う小学生6人と1つの居住スペースで生活をしています。室内にはリビングや台所に加えて小さな部屋が3部屋あり、寝るときは1部屋2人づつに分かれて寝ています。6人兄弟のようなイメージで、職員が生活のケアなどをしています。

施設で暮らす子どもたちの背景は様々です。突然の親の事故や病気、ネグレクト、虐待、妊娠中の薬物摂取、受刑者の出産…。児童相談所から「家庭で過ごすことが適当でない」と判断された子どもたちが、施設で暮らすことになります。
ただ、広島修道院の山村拓哉院長は、「子どもは家庭で養育された方が良い」と話します。

山村院長「子どもにとって養育者は『ずっとこの人が私のことを見てくれる』という安定した見通しの中で育つ方が良いんです。でも施設で育つと職員体制が変わったりということがありますし、そもそも集団で育つので子ども1人1人の思いがくみとりにくいし実現しにくい。」
里親の元での生活は、特定の大人との関係を築くことができます。
里親制度と養子縁組は違います。養子縁組は法的にも親子関係となる一方で、里親制度はあくまでも「預かる」制度。子どもが成人して自立できると判断されると、養育期間は終了となります。また、子どもとの関係がうまくいかずに関係を解消する「委託解除」となることも少なくありません。

里親にも様々な種類があります。長期間預かる「養育里親」の他に、かずまくんのように週末や長期休みのみを里親の元で過ごす「週末里親」があります。
「週末里親」は、施設で生活を続ける子にとって「家庭生活が体験できる」点にメリットがあります。将来自分の家庭を持つときに、家庭での生活を知っているか知らないかでは大きな差となります。
かずまくんは月に1度、土日をあきこさん夫婦の家庭で過ごしています。