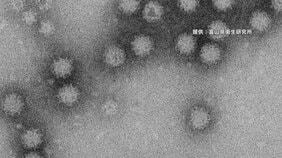「大きな成果というのは時期尚早」専門家が指摘する課題

同行した県関係者
「翁長知事との違いは、個別面談が充実していたこと。学術調査などで特別報告者による沖縄訪問を実現できれば。次に繋がる“種まき”ができた」
県によるとPFASなどアメリカ軍基地由来の環境汚染の現状を説明した知事に対し、有害物質が専門の特別報告者は「100%理解している」と応じた上で、調査での沖縄訪問に期待を示したということです。
一方、今回の国連出張について県議会野党会派はー
県議会 野党関係者
「基地問題=人権問題ではない。辺野古移設工事は法的に手続き上の瑕疵はなく、沖縄の自治権が無視されているとは思えない。議会でも厳しく追及する。成果はない」
国際人権法に詳しい琉球大学の阿部藹(あべあい)客員研究員は「大きな成果」として上げられている、特別報告者との面談について次のように指摘します。
琉球大学 阿部客員研究員
「実は大きな成果というにはまだ時期尚早。というのは、声明を発表したり、特別報告者に会ったりしただけでは、国連の担当者に具体的な行動を期待するということはなかなか難しい」
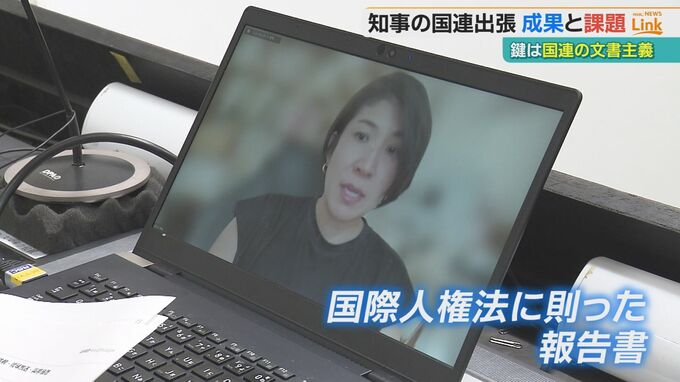
『特別報告者』を動かすには、県の現状を示すデータを含む国際人権法に則った報告書の提出が重要だといいます。
琉球大学 阿部客員研究員
「そもそも国連というのが文書主義なんですね。何かの情報提供をするときに書面で提出することがとても大事なんですね」
「特別報告者は条約や国連決議などに基づいて行動されるので、面談で提起した人権問題を国際人権法にのっとった形で報告書を作って、その報告書をまずフォローアップとして提出をするっていうことが、必ず必要になってくるかなと思います」
面談相手との継続的、且つより具体的なやり取りが、国連出張の成果を示し、基地問題の解決に向けて突破口を見出すカギとなりそうです。
【記者MEMO】
県によりますと「口頭声明」ではなく「文書声明」という形で訴えることもできましたが、対外的なアピールも含めて知事が直接口頭で伝えるのがより効果的と判断したそうです。
今後は、国連を動かす報告書の作成に向けたノウハウの構築など継続的な取り組みが重要となります。