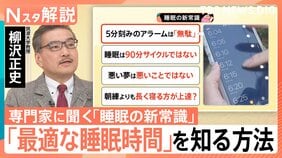フィジーやサモアなどで水産業に携わる人たちがJICA=国際協力機構の研修員として沖縄を訪れていて、観光業などを活用した漁業の運営の仕組みなどについて学んでいます。
これはJICA沖縄が主催する支援事業で、フィジーやサモアなどの8か国から水産業の運営などに携わる研修員8人が先月から沖縄を訪れています。
この日は読谷村漁業協同組合で捕獲から加工、販売までの一連の流れを学びました。
サモア農業水産省上級漁業官 タウエファ・アウタァヴさん
「この研修は実用的なだけでなく、私たちのような途上国が安定した食の供給や収入を得るための力を伸ばすうえでとても大事です」
サモアなどの島しょ国で重要な収入源となる水産業ですが、捕獲の技術のみならず販売などを通した安定した収入の確保も課題となっています。
プロジェクトの運営に携わる吉田さんは、魚の種類は多いものの種類ごとの漁獲量が少ないなど共通の課題がある沖縄だからこそ参考になると話します。
琉球環境マネジメントサービス 吉田透社長
「社会的な規模の大きさも非常に似ていて、一つの集落が300人とか500人くらい。その中でどうやって水産資源管理をしたり、販売の工夫をしたりするかに取り組んでいる。沖縄の事例は、島しょ国の皆さんに参考になる」
読谷漁協では6年前にセリ市場や直売所、飲食店などが入る複合施設をつくり、セリでの収入が少ない場合でも飲食店などで安定した収入が得られる仕組みを構築していて、研修員らは共通点の多い沖縄の水産業の工夫について説明を受けていました。
研修員は今月末まで沖縄に滞在する予定で、ほかにも与那国島など県内各地の漁協の取り組みを学ぶ予定です。