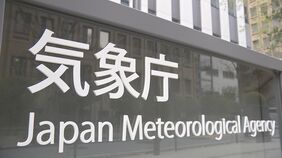80年前の3月26日、米軍が慶良間諸島に上陸を開始し、沖縄戦が始まりました。米軍が最初に上陸した座間味村ではきょう、犠牲になった人々を悼む慰霊祭が開かれました。
太平洋戦争末期、日米両軍による激しい地上戦が行われた沖縄では、軍民合わせて20万人あまりが犠牲となり、県民の4人に1人が命を落としました。
80年前に米軍が上陸し、いわゆる「集団自決」などによって多くの住民が犠牲となった座間味村では26日、玉城知事も参列し慰霊祭が開かれました。
▼玉城デニー知事
「島の住民が凄惨な集団死に追い込まれるなど、多くの住民の平穏な生活とかけがえのない命が奪われました」
慰霊祭には、遺族や集団自決を生き延びた人たちも集まり、犠牲者に鎮魂の祈りをささげました。
▼集団自決の生存者
「いけるところまで生きていこうということで逃げ回ったわけですね」「二度とああいう悲惨な戦争を起こしちゃいけないということですね。そしてその事実を後世に風化しないように継承していきたいなと、そう思っています」
▼遺族
「兄2人がここ(平和之塔)にまつられている。一日でも早く兄の骨が戻ってきたらいいなと思う」
▼座間味島で戦争を体験
「この戦争というのを体験して、目の前を本当に火の玉が飛んでるのも体験しました」
▼父親を座間味島で亡くす
「写真でしか顔が分からないけど、僕が生まれて1週間くらいで(父が)ここにきた」「父がここに眠っているということは、ここに来たよ、会えたよいう感じですね」

体験者や遺族の高齢化が進むなか、沖縄戦の実相や島で起きた悲劇をどう語り継いでいくのかが課題となっています。