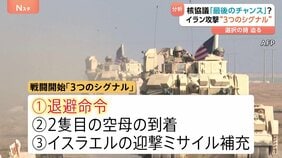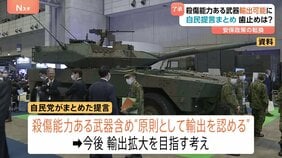「治水に限界」は大前提
前回の豪雨ではおよそ200戸が浸水した大肥川流域でも河川改修の効果が見られ、今回の浸水の規模は小さかったとみられています。一方、小野地区の和田集落に住む和田秀秋さんは、今回の豪雨ではこれまで経験のない被害だったと話します。

小野地区和田集落・和田秀秋さん
「73年住んでいるが比べ物にならないくらい今度は大きな被害です」
6年前と3年前の豪雨で自宅の裏山が崩れ、県が2度にわたり崩落防止工事と護岸の整備を実施していました。しかし、今回は想定していなかった自宅の正面から濁流が押しよせ、初めて浸水被害に見舞われました。
小野地区和田集落・和田秀秋さん
「いま『全伐』と言って樹木を全部切ってしまう。切った杉と土砂が一緒になって谷がつまる。そのため他のところからザーッと水が流れてきた」

6年前の豪雨以降、地区を離れた人も少なくありませんが、和田さんはこの地に住み続けたいと考えています。
小野地区和田集落・和田秀秋さん
「(息子には)帰って来いとはいえませんよね、こういう所を見ますと。先祖の土地があったり田んぼがあったり、墓もこの上にあるものですから自分は最後まで守っていきたいと思っている」
地球温暖化により記録的な豪雨が数年ごとに発生する中、小松名誉教授は従来の治水対策には限界があると指摘します。
九州大学(防災工学)・小松利光名誉教授
「いま地球温暖化がどんどん進展していますから前回被害を受けた災害よりもっとすごいものがくる可能性の方が高い。いわゆるインフラによる治水には限界があるということはもう大前提。自分の住んでいる地域がどれくらいリスクがあるかというのを認識しておくことがとにかく一番大事です」
行政による治水対策に限界が見える中、住民一人一人が水害リスクの高まりを認識し、行動していくことがますます重要になってきます。