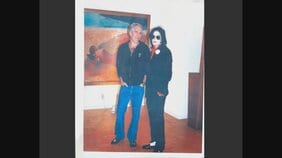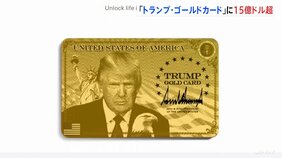全国の天然ヒジキの主要産地で軒並み不良が続いていて、業者も増えて乱獲に拍車がかかり、資源の枯渇が危惧されています。こうした中、日本一の水揚げ量を誇る大分県では、天然ものの乱獲を防ぎ、生産量の拡大にもつながる技術開発が全国に先駆けて進められています。
乱獲を防ぐ100Mのロープ…「経費かからず楽なもの」
家庭料理の定番惣菜「ヒジキ」。今、大分県内で生産されるヒジキが全国で注目を集めています。大分県国東市の沖合、漁船に乗って5分ほどの場所にあるヒジキの養殖場。1メートルほどの長さに生長したヒジキがロープづたいにびっしりと生い茂っています。漁師の濱松豊信さんは天然ものの収穫とともに、5年前から養殖にもチャレンジしています。
(県漁協くにさき支店・濱松豊信さん)「今年は全体的にずっと1メートル以上伸びている。天然も良かったし、養殖の方も順調」
養殖方法は100メートルのロープに5センチ間隔で天然ヒジキの種苗を挟み込むだけ。一直線に設置し、ロープ1本につき乾燥状態で最大100キロ収穫できるといいます。濱松さんは去年11月、ロープ9本を設置していて、半年の月日を経て5月下旬にも収穫を迎えます。
(県漁協くにさき支店濱松豊信さん)「エサもいらないし、港から近くて経費もかからないし、自然と大きくなってくれるので、それは楽なもの。県も指導してくれるし、みんなで頑張ってやろうと」

この養殖方法を研究し濱松さんに指導したのが、豊後高田市にある県の北部水産グループです。
(県北部水産グループ・徳丸泰久さん)「天然ヒジキの主要産地が軒並み不良のため単価がよく、業者も増えて乱獲に拍車がかかっているので、私たちの養殖の研究で支援している状況」