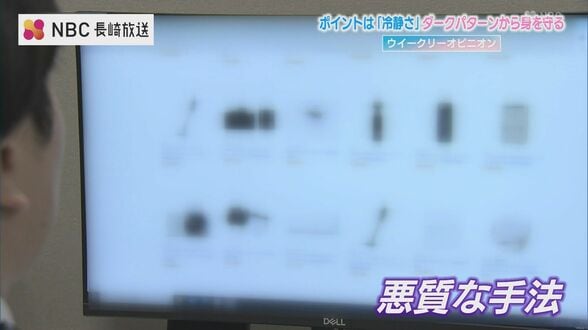■ “ジャパンブリ”が世界を席巻!?

征矢野 教授:
「やっぱりいつか世界では、みんなが『ノルウェーサーモン』を食べてるんじゃなくて『ジャパンブリ』を食べている──

我々『ジャパンブリ プロジェクト』というのを考えてまして、いつかはノルウェーサーモンに代わって世界がジャパンブリを食べる、そういった未来をつくっていこうと今、思ってます」

その実現に向けて、征矢野 教授らは、最新のIT技術の導入や、新たな養殖技術の開発による水産業の改革に取り組んでいます。



生産者の負担軽減だけでなく、限りある資源を保護し、水産業を持続的に発展させるためのこの取り組みは『ながさきBLUEエコノミー』と呼ばれています。
征矢野 教授:
「実は“BLUEエコノミー”って非常に大事な考え方で、海の生物とか環境を守りながら、そこにある資源を持続的に利用していこうという考え方なんです。まさにSDGsに基づく考え方なんですけれども、海を守りながらそこにいる魚たちをどうやって食卓に上げていくのか、それを産学官 一体になってやっていこうとしているところなんです」
ですが、いくら養殖が進歩しても“売れなければ”意味がありません。
いかに“魚が売れる仕組み”をつくっていくのか ──
■ 地元の水産資源を食べ その魅力を知る
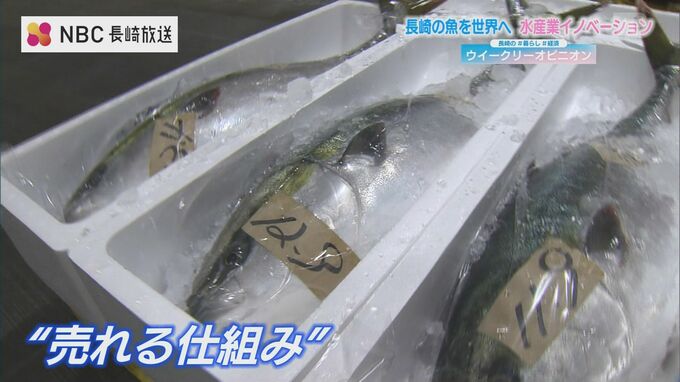
そのためには水産関係者の努力ははもちろん、地元の人たちに魚を食べてもらうような取り組みも必要だと征矢野 教授は考えています。

征矢野 教授:
「一番大事なのは“食べるということ”です。生産者がつくったものを長崎の方が誇りをもって、自信をもって食べるかどうかなんですね。そこのところが実は長崎は弱いところなんですよ。
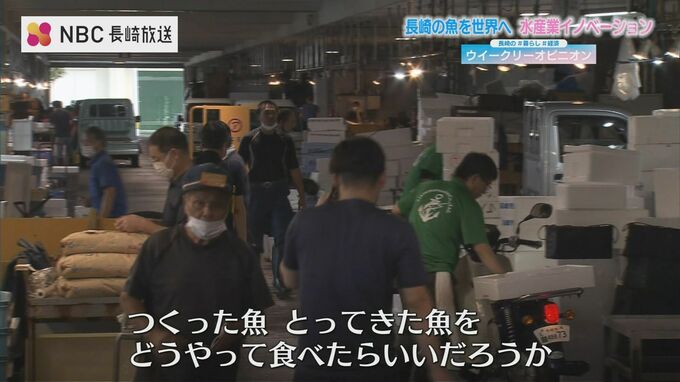
『作った魚』『獲ってきた魚』を“どうやって食べたらいいだろうか”(をもっと知る)。

あるいは長崎はもうひとつの産業は“観光”ですから、(長崎に)やって来た人たちに“どうやって提供したらいいだろうか”(を考えていく)。
やっぱり地元の人たちが一生懸命食べて、誇りを持って食べていかないと、それは外から来た方々に伝わらないと思うんですよね」
魚の消費拡大や地産地消を進めようと、他の『一次産業』や『観光産業』などと連携して “長崎の食の拠点”を作る構想も動きはじめています。
征矢野 教授:
「長崎の色んな食材を集めて“地元の人”も“観光客”も集まるような──我々いま『長崎マルシェ』って呼んでるんですけど…それを長崎に作る。市民の人たちがそれを盛り上げていく。
もちろん水産の活性化にもなるんですけど、それだけではなくて地域全体の活性化になるんじゃないかと思ってます」